すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
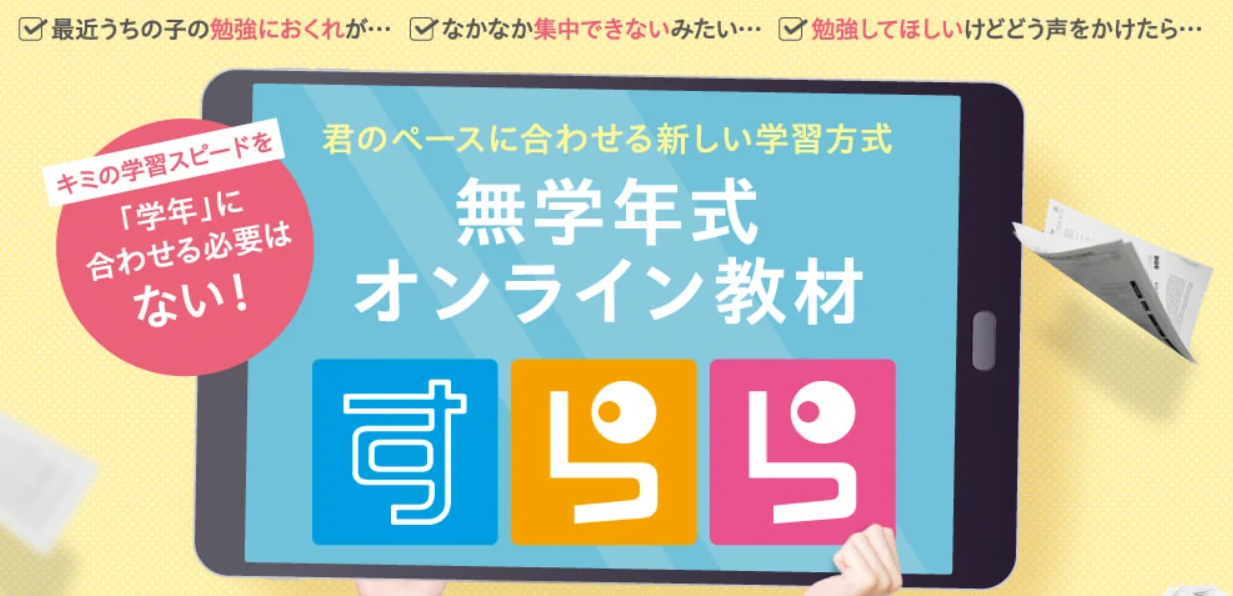
「すららはうざい」という声を見かけることがありますが、実際のところどうなのでしょうか?すららは、無学年式の学習システムや、対話型の授業スタイルが特徴のオンライン教材です。
特に、自分のペースで学びたい子どもや、学校の授業にうまく適応できない子どもにとっては、大きなメリットがあります。
本記事では、すららの魅力を詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
すららのおすすめポイントをまとめました
すららは、従来のオンライン学習サービスとは異なり、学年に縛られずに学べる無学年式や、親の負担を減らすサポート体制が充実しています。
以下に、すららの特徴をまとめました。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
学校の授業では、学年ごとに決まった内容を学習するため、理解が追いつかない場合でも次に進んでしまうことがあります。
一方、すららの「無学年式」では、子ども一人ひとりの理解度やペースに合わせて学習を進めることができるので、学校の授業についていけない子や、逆にもっと先の内容を学びたい子にもぴったりです。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
すららでは、学年の枠にとらわれることなく、苦手な科目は基礎に戻って学習し、得意な科目はどんどん先に進むことができます。
たとえば、小学1年生でも英語が得意なら中学レベルの英語を学ぶことが可能ですし、中学生が小学校の算数に戻って学び直すこともできます。
この柔軟性が、すららの大きな魅力の一つです。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
学校の授業では、一度つまずいてしまうと、そのまま置いていかれることが多いですが、すららではそんな心配がありません。
わからない単元があれば、AIが自動的に分析して適切な学習内容を提案してくれるため、「理解できないまま次に進む」ということがありません。
逆に、得意な科目はどんどん先に進めるので、学習意欲を高めることができます。
こうした自由な学習スタイルが、多くの子どもたちに支持されている理由です。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
子どもが自宅で学習するときに、「一人で勉強しているとつまらない」「教科書だけでは理解しにくい」と感じることは少なくありません。
すららでは、アニメキャラクターが「先生役」となり、対話形式で授業が進むため、まるで誰かと一緒に勉強しているような感覚で学べます。
また、映像やアニメーションを活用しているため、難しい内容でも直感的に理解しやすいのが特徴です。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
すららの授業では、アニメキャラクターが先生の役割を担い、子どもと対話しながら学習を進めていきます。
単なる一方的な講義ではなく、「これはどう思う?」と質問を投げかけてくれるので、受け身になりにくく、子どもが自ら考える力を育てることができます。
まるで家庭教師とマンツーマンで勉強しているような感覚で学習できるのが魅力です。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
文字だけの説明では理解が難しい内容も、すららの授業ならアニメーションで分かりやすく解説してくれます。
たとえば、算数の「割合」や理科の「天体の動き」など、抽象的な概念も映像を使って説明されるので、視覚的に理解しやすくなります。
図や動きを活用することで、頭の中でイメージしやすくなり、記憶にも定着しやすくなるのが特徴です。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
すららの授業では、キャラクターが学習の進捗を見守り、頑張ったときには褒めてくれます。
特に、勉強に苦手意識を持っている子どもにとって、「よく頑張ったね!」「すごいね!」と声をかけてもらえることは、大きな励みになります。
ゲーム感覚で楽しく学べるため、「飽きっぽくて続かない」と悩んでいる子どもでも、やる気を維持しやすいのがメリットです。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
子どもの家庭学習をサポートするのは、親にとって大きな負担になることがあります。
「何をどのくらいやらせればいいのか分からない」「毎日学習を見守る時間がない」と悩む家庭も多いでしょう。
すららには「すららコーチ」と呼ばれる専門のコーチがついており、学習計画の作成から進捗フォローまでサポートしてくれるため、親が細かく管理する必要がありません。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
すららコーチは、子ども一人ひとりに合わせた学習計画を作成し、進捗を確認しながら適切なアドバイスをしてくれます。
子どもがどの教科をどのくらい勉強すればいいのかを決めるのは意外と難しいものですが、プロがしっかり管理してくれるので、無理なく継続できる環境が整います。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららコーチは、単に一般的な学習プランを提供するのではなく、子どもの性格や学習スタイルに応じてオーダーメイドの学習計画を立ててくれます。
「この子は集中力が続きにくいから短時間で区切って進めよう」「英語は得意だから少し難しめの内容を取り入れよう」といった工夫ができるので、無理なく楽しく学習を続けることができます。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
学習中に分からないことがあったとき、親がすぐに教えてあげられるとは限りません。
そんなときでも、すららコーチに直接質問や相談ができるため、親がつきっきりでサポートする必要はありません。
「子どもに学習を任せたいけど、ちゃんと進められるか心配」と感じる家庭にとっては、頼れるコーチがいることで安心して見守ることができます。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは、発達障害のある子どもや、不登校で学校の授業に遅れてしまった子どもでも無理なく学習を続けられるように設計されています。
一般的な学習教材では、決められた進度で進めなければならず、ついていけないと苦しさを感じることがありますが、すららは一人ひとりのペースに合わせて学べるので、学習へのハードルを大きく下げてくれます。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、その優れた学習支援システムが評価され、文部科学大臣賞を受賞しています。
これは、教育分野において特に優れた取り組みに贈られる賞であり、多くの教育機関でも導入されている実績があります。
信頼できる学習ツールであることが、この受賞によって証明されています。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
すららは、発達障害を持つ子どもにも適した学習設計がされているため、注意がそれやすい子や、特定の分野で理解が難しい子どもでも安心して学べます。
たとえば、ADHDの子どもは集中力が続きにくい傾向がありますが、すららの対話型授業は飽きにくく、興味を持ちやすい工夫がされています。
学習障害(LD)の子どもにとっても、文字だけでなく映像や音声を活用した授業があるため、理解しやすい環境が整っています。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
不登校の子どもにとって、学校の授業に遅れてしまうことは大きな不安材料になります。
しかし、すららなら学校の授業とは関係なく、自分のペースで学習を進めることができます。
「学年に縛られない学習」なので、無理にクラスの進度に合わせる必要がなく、理解が追いつくまでじっくり取り組めるのが特徴です。
また、対話型の授業なので、一人で学ぶ孤独感を軽減できるのもポイントです。
つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
すららにはAI機能が搭載されており、子どもがどこでつまずいているのかを解析し、理解不足の部分を自動で出題してくれます。
これにより、「どこが分からないのか分からない」という状況になりにくく、効率よく学習を進めることができます。
間違えた問題の傾向を分析して、適切な復習問題を出題してくれるので、学習の抜け漏れを防ぐことができます。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
学習を続けるうえで、「本当に力がついているのか?」と不安になることもあります。
すららでは、オンラインテストやリアルタイム学力分析の機能があり、どれだけ理解できているのかをすぐに確認することができます。
学習の成果が目に見える形で分かるため、子ども自身のモチベーションアップにもつながります。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
すららでは、学習後に小テストが用意されており、問題に間違えるとすぐにフィードバックが受けられます。
「なぜ間違えたのか」をその場で理解し、すぐに修正できるので、間違えたまま放置することがありません。
これにより、知識を確実に定着させることができます。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
学習が進んでいるように見えても、実際にはどこが苦手なのか気づきにくいものです。
すららではAIが定着度を診断し、苦手な分野をピンポイントで把握してくれます。
その結果に基づいて対策問題が自動で出題されるため、苦手を克服しながら学習を進めることができます。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
すららでは、学習の進捗状況やテストの結果を保護者にレポートとして配信する機能があります。
これにより、「ちゃんと学習しているのか?」「どこが得意で、どこが苦手なのか?」といったことを親が把握しやすくなります。
学習状況を見える化することで、保護者も安心して子どもの学習を見守ることができます。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
すららの英語学習は、「聞く・読む・話す」の3技能に対応しており、総合的に英語力を伸ばすことができます。
一般的なオンライン教材ではリーディングやリスニングが中心になりがちですが、すららではスピーキング練習も取り入れられているため、実践的な英語力を養うことができます。
英検対策にも活用できるので、小学生から中学生、高校生まで幅広い層におすすめです。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
英語のリスニング力を高めるためには、正しい発音や自然なイントネーションに慣れることが重要です。
すららでは、ネイティブスピーカーの音声を使ったリスニング学習ができるので、実際の会話に近い発音を身につけることができます。
英語の授業だけではリスニングの機会が少ないと感じる子どもにとっても、耳を鍛える貴重な学習環境になります。
音読チェックでスピーキング練習ができる
英語を「話す力」を鍛えるために、すららでは音読チェック機能が用意されています。
音読することで発音のクセを修正し、正しい発音やリズムを身につけることができます。
英語の授業ではスピーキングの練習時間が限られているため、自宅でしっかり発話の練習ができるのは大きなメリットです。
英検の面接対策にも役立つため、実践的な英語力を高めたい人にぴったりです。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
英語学習でつまずきやすい単語や文法の理解も、すららならアニメーションを使ってわかりやすく解説してくれます。
文字だけの説明では理解しづらい文法ルールも、視覚的に学べるためスムーズに習得できます。
英検対策としても役立ち、リーディングやリスニングだけでなく、スピーキングの準備までしっかりサポートしてくれるので、バランスよく英語力を伸ばせます。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららの料金体系は、他のオンライン教材と比べてもユニークな特徴があります。
それは「1契約で兄弟も一緒に使える」という点です。
通常、オンライン学習サービスは1人1契約が基本ですが、すららでは1つの契約で複数人が利用可能なので、兄弟がいる家庭にとって非常にコスパの良いサービスです。
さらに、必要な科目だけを追加できるため、無駄なく学習できるのもポイントです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
すららは、1つの契約で兄弟が一緒に学習できるシステムになっています。
例えば、兄が中学生で妹が小学生の場合でも、それぞれの学年に応じた学習内容を利用できるので、兄弟それぞれに契約する必要がありません。
追加料金なしで兄弟が学べるため、家族全員で活用することができ、コストパフォーマンスの面でも優れています。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
兄弟で学習をさせたい場合、通常はそれぞれ別の教材を契約する必要がありますが、すららなら1契約で済むため、教育費を大幅に節約できます。
例えば、小学生の兄が算数と国語を学び、中学生の妹が数学と英語を学ぶといった使い方ができるので、学年が異なっていても無駄がありません。
特に、複数の子どもを持つ家庭には非常におすすめです。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
すららでは、必要な科目だけを選んで追加することができるため、「この科目だけ勉強したい」というニーズに柔軟に対応できます。
例えば、英語だけ強化したい場合や、数学だけ苦手だから重点的に学びたい場合など、自分の目的に合わせてカスタマイズできます。
不要な科目にお金をかける必要がないため、効率よく学習できるのが魅力です。

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
家庭学習用のタブレット教材は数多くありますが、その中でも「すらら」は独自の特徴を持ったオンライン学習システムです。
一方で、「すららはうざい」「使いにくい」といった声を耳にすることもあります。
しかし、それはすららの仕組みを十分に理解していないことが原因かもしれません。
すららは、他の教材にはない対人サポートや、不登校・発達障害の子どもにも対応できるシステムを備えているのが強みです。
この記事では、すららの具体的なメリットについて詳しく解説します。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
すららの大きな魅力のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの存在です。
一般的なタブレット教材は、基本的に子どもが一人で学習を進める形式ですが、すららではプロのコーチが学習の進捗を管理し、子どもが無理なく学習を続けられるようサポートしてくれます。
これにより、「うちの子は一人で勉強を続けられるか不安…」といった悩みを持つ家庭でも安心して導入できます。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららコーチは、単なる学習サポートではなく、子どもの学習状況をしっかり把握し、適切なアドバイスを行ってくれるのが特徴です。
「学習ペースが遅れていないか」「つまずいている部分はどこか」などを細かく分析し、必要に応じてサポートしてくれるため、ただのタブレット学習とは違い、しっかりとしたフォロー体制が整っています。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
子どもによって、得意な科目や苦手な科目、勉強のペースはさまざまです。
すららでは、コーチがそれぞれの子どもに合った学習スケジュールを作成し、無理のない範囲で学習を進められるよう調整してくれます。
「今日は何を勉強すればいいの?」と迷うことなく、計画的に学習を進めることができるため、子どもも安心して勉強に取り組めます。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららは、一般的な学習教材と異なり、不登校の子どもや発達障害の子どもにも対応した設計になっています。
文部科学省にも認められた教材であり、多くの学校でも学習支援ツールとして採用されています。
特に、不登校の子どもにとっては「学校の授業についていけるか不安…」という悩みを解消し、安心して学習を続けられる環境を提供してくれます。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、文部科学省の推薦を受け、多くの学校で学習支援教材として採用されています。
特に、不登校の子どもや発達障害のある子どもに適した学習カリキュラムが組まれており、「学校の授業についていけない」「学年に縛られず自分のペースで学びたい」といったニーズに応えられる設計になっています。
通常の学習教材では対応が難しいケースでも、すららなら柔軟に学習を進められます。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららを活用することで、「学校に通えない=学習の遅れが心配」という不安を解消できるだけでなく、自治体や学校によっては、すららでの学習が「出席扱い」と認められるケースもあります。
これは、すららが文科省の基準を満たした学習教材であり、適切な学習支援ツールとして評価されている証拠です。
学習の遅れを心配せず、自宅で無理なく学べるのは、すららならではのメリットです。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
発達障害(ASD・ADHD・LDなど)の子どもにとって、一般的な授業スタイルでは集中しづらかったり、理解しにくかったりすることがあります。
すららでは、そうした特性を持つ子どもにも学びやすいカリキュラムが用意されており、無理なく学習を進められるよう設計されています。
例えば、短い時間で区切って学習できるモードや、視覚的に理解しやすいアニメーション授業など、個々の学習スタイルに合わせた学び方ができるのが特徴です。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららの大きな特徴のひとつが、学年にとらわれない「無学年学習」システムです。
一般的な学習教材では、学年ごとにカリキュラムが決められているため、理解が追いつかなくても次に進まざるを得ないことが多いですが、すららでは自分のペースで自由に学習を進めることができます。
得意な科目はどんどん先取りし、苦手な科目は基礎からやり直すことができるので、効率的に学習を進められるのがポイントです。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
通常の学校教育では、学年ごとに決められた内容を学ぶため、「授業についていけなくなったら、そのまま置いていかれる」「得意な科目も学年の進度に縛られる」といった問題が発生しがちです。
しかし、すららでは学年の枠を超えて自由に学ぶことができるので、例えば小学1年生が中学英語に挑戦したり、中学2年生が小学校の算数を復習したりすることが可能です。
自分に合った学習ペースで進められるため、苦手を克服しやすく、得意分野は伸ばしやすい環境が整っています。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害のある子どもは、特定の科目や単元でつまずきやすく、通常の学校教育のペースでは理解が追いつかないことも少なくありません。
すららの無学年学習なら、「わからないところをそのままにしない」学習ができるため、焦らずじっくり学ぶことができます。
逆に、得意な分野はどんどん進めることができるため、興味や関心を持ちやすく、モチベーションを維持しやすいのも大きなメリットです。
学習のペースを自分でコントロールできることで、学ぶことに対するストレスが軽減され、楽しく学習を継続できる環境が整います。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららの学習サポートのもう一つの大きな特徴は、「AI診断」と「対人コーチング」の両方を組み合わせた学習設計ができることです。
最近では、AIを活用したオンライン学習サービスも増えていますが、すららはAIによるデータ分析だけでなく、人間のコーチが学習状況をしっかり確認し、必要な調整を行ってくれるのがポイントです。
AIの強みと人間のサポートを掛け合わせることで、一人ひとりに最適な学習計画を作成し、より効果的な学習を実現します。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
AIが学習データを分析し、「どこでつまずいているか」「どの単元を復習すべきか」を自動で判断してくれるため、無駄なく効率的な学習が可能になります。
しかし、AIだけでは個々の学習状況を完全に把握することは難しいため、すららでは対人コーチによるサポートを組み合わせています。
コーチが学習の進め方をチェックし、適切なアドバイスを行うことで、「自分に合った学習法がわからない」「計画通りに進められるか不安」といった悩みを解決できます。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIはデータ分析が得意ですが、子どもの学習意欲やモチベーションの変化を細かく察知することは難しい場合があります。
すららでは、コーチが定期的に学習状況を確認し、必要に応じて学習計画を修正したり、励ましの言葉をかけたりすることで、学習を続けやすい環境を整えてくれます。
「一人で勉強するのは不安…」という子どもでも、コーチのサポートがあることで、安心して学習を進めることができます。
AIと人間のWサポートにより、最適な学習環境を提供できるのが、すららの大きな強みです。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
すららは、タブレット学習でありながら「記述力」を鍛えることができる珍しい教材です。
一般的なオンライン学習は選択式の問題が中心で、文章を書いて考える力を育むのが難しいと言われています。
しかし、すららでは「論理的に書く力」や「説明する力」に重点を置いたカリキュラムが組まれており、デジタル環境でも記述のトレーニングを積むことが可能です。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
記述力を伸ばすためには、「自分の考えを整理して伝える練習」が必要です。
すららでは、単に問題を解くだけでなく、学んだことを自分の言葉で説明するトレーニングが組み込まれています。
「なぜそうなるのか?」を論理的に考えながら記述することで、思考力や表現力が鍛えられます。
これは、テスト対策だけでなく、将来的に役立つスキルとしても重要です。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
オンライン学習の多くは、記述問題に対応しておらず、「読んで答える」「選択肢を選ぶ」形式が主流です。
しかし、すららではデジタル上で記述練習ができるため、紙を使わなくても文章を書く力を鍛えることができます。
読解力を身につけながら記述力を高められる教材は珍しく、国語の学習を重視したい方にとっても大きなメリットです。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
すららは、学習の中断と再開がしやすい仕組みになっているため、「一度やめてしまうと、再開するのが難しい」という心配がありません。
学習ペースに波がある子どもや、不登校・発達障害のある子どもにとっては、無理なく続けられる柔軟な学習環境が重要です。
すららなら、自分のペースに合わせていつでも再開できるので、途中で学習を中断しても安心です。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
すららでは、学習履歴がすべて記録されているため、途中で学習をやめても、再開するときに「どこからやればいいのかわからない」と迷うことがありません。
学習進捗が自動で保存されるので、以前学んでいた内容をすぐに確認し、スムーズに学習を再開できます。
「一度やめたら追いつけない」というプレッシャーがないため、無理なく学び続けられるのがポイントです。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
不登校や発達障害の子どもは、日によって学習のペースが変わることがあります。
「今日は集中できない」「しばらく休みたい」といった状況になったときに、無理に続けるのではなく、自分のタイミングで再開できる環境があることが大切です。
すららは、一度中断しても復帰しやすいため、自分のリズムで学習を進められるのが大きなメリットです。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、単なるオンライン学習教材ではなく、教育機関とも連携しているのが特徴です。
不登校支援の一環として、すららでの学習を「出席扱い」と認める学校が増えており、自治体や教育委員会との連携実績も豊富です。
そのため、「学校に行けなくても学習の遅れを心配せずに進めたい」と考える家庭にとって、安心できる学習環境を提供してくれます。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
不登校の子どもにとって、「出席日数が足りなくなるのでは…」という不安は大きな問題です。
しかし、すららを利用して学習を続けていれば、自治体や学校によっては「出席扱い」と認められるケースが多くあります。
これは、すららが文部科学省の基準を満たした学習教材として評価されているためであり、学校に通えなくても学習の遅れを取り戻す手段として有効です。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは、不登校支援のために学校や病院とも連携しており、単なる自宅学習ツールではなく、教育支援の一環として活用されています。
例えば、病気で長期間学校に通えない子どもがすららを使って学習を続けることで、復帰後の授業にもスムーズに対応できるようになります。
また、特別支援教育の現場でも導入されているため、発達障害や学習障害のある子どもにとっても、安心して利用できる教材です。

【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは多くのメリットがある一方で、「うざい」と感じる人がいるのも事実です。
どんな学習教材にも向き不向きがあり、すららも全員にとって完璧な学習ツールとは言い切れません。
では、なぜ「うざい」と感じる人がいるのか?ここでは、すららのデメリットと、利用者が感じる不満点について紹介します。
これを理解することで、自分やお子さんにすららが合うかどうかを判断する材料になるはずです。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららの大きな特徴のひとつに「すららコーチ」のサポートがあります。
学習の進捗を管理し、計画的に進められるようフォローしてくれる点はメリットですが、人によっては「連絡が多すぎる」「干渉されすぎている」と感じることもあるようです。
特に、自分のペースで学習を進めたい子どもにとっては、サポートが過剰に感じることがあるかもしれません。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららコーチは、学習計画を立てたり進捗をチェックしたりと、子どもが途中で挫折しないようにサポートしてくれる存在です。
しかし、すべての子どもが「サポートを必要としている」とは限りません。
「自分のペースでやりたい」「誰にも干渉されずに進めたい」というタイプの子どもにとっては、コーチの存在が逆にプレッシャーになることもあります。
また、親としては「しっかり見守ってくれるのはありがたい」と感じる一方で、「もう少し自由に学ばせてほしい」と思うケースもあるようです。
そのため、すららを利用する際は、子どもの学習スタイルに合っているかどうかを確認することが大切です。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららは、AIが自動で学習計画を作成し、どの単元をどのくらい学習すればよいかを提示してくれます。
効率的に学ぶための仕組みですが、「自分のペースでやりたい」「自由に学びたい」と思っている子どもにとっては、「やらされている」と感じることがあるかもしれません。
特に、スケジュール通りに進められないと、「遅れている」「ちゃんとやらなきゃ」とプレッシャーに感じることがあるようです。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
すららのAIは、学習データを分析し、効率よく学べるようにスケジュールを組んでくれます。
しかし、「今日は気分が乗らない」「もう少しじっくり復習したい」と思っても、システム上のスケジュールに追われるように感じることがあるようです。
また、「やるべきことがどんどん表示される」と、「やらなきゃいけないことが増えているように感じる」という声もあります。
自由度が少ないと感じると、勉強が義務のようになり、学習意欲が低下してしまうことも考えられます。
そのため、すららを利用する際は、子どもが「このスタイルで勉強できそうか?」を事前に確認することが大切です。
学習計画をある程度自分で調整しながら進めたい場合は、親子で相談しながら活用するのがよいでしょう。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららの授業は、アニメーションキャラクターがナビゲーションをしてくれるのが特徴です。
親しみやすく、楽しく学習を進められる工夫がされていますが、一方で「キャラクターが子どもっぽい」「演出がくどい」と感じる人もいます。
特に、高学年や思春期の子どもにとっては、「もっとシンプルに勉強したい」と思うこともあるようです。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
低学年の子どもには、キャラクターが授業を進めてくれるスタイルは分かりやすく、学習のハードルを下げるメリットがあります。
しかし、高学年や中学生になると、「子どもっぽい」「説明がまどろっこしい」と感じる子も出てきます。
また、すららは対話型授業のため、キャラクターが何度も話しかけてくる演出がありますが、「いちいち話が長い」「さっさと問題を解きたい」という子どもにとっては、少しテンポが遅く感じられることもあります。
そのため、「アニメ風の授業スタイルが合うかどうか?」を事前に確認しておくことが大切です。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
すららは、無料体験や資料請求をすると、その後に勧誘やフォローの連絡が来ることがあります。
教育サービスとして、しっかりと説明を行う意図があるのですが、「営業がしつこい」と感じる人もいるようです。
特に、興味があって資料を取り寄せたものの、まだ申し込むつもりがない場合、頻繁な連絡が負担に感じることがあるかもしれません。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
すららの口コミを調べると、「営業がしつこい」「勧誘の電話が多い」という声を目にすることがあります。
もちろん、親切なサポートと感じる人もいますが、「一度問い合わせただけで何度も連絡が来るのが嫌だった」という意見もあります。
SNSでは、こうした勧誘の印象が「うざい」と言われることがあり、営業スタイルが合わないと感じる人もいるようです。
もし勧誘が気になる場合は、「今後の連絡は不要」とはっきり伝えるか、メールのみの対応を希望することで、不要なストレスを減らすことができます。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららは、一般的なタブレット学習教材と比べると料金がやや高めに設定されています。
無学年学習や対人サポートが充実している分、他の教材よりもコストがかかるのは仕方のない部分ですが、「この料金に見合う効果があるのか?」と疑問を持つ人もいるようです。
特に、子どもが積極的に学習に取り組めない場合、親としては「せっかくお金を払っているのに…」と不安を感じることもあるかもしれません。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
すららは、基本的に「自分で学習を進める」スタイルの教材です。
そのため、子どもが積極的に学習しないと、せっかくの教材も十分に活用できず、勉強の成果を実感しにくくなります。
「タブレットを開かない」「すぐ飽きてしまう」といった場合、親としては「本当にこの料金を払う価値があるのか?」と疑問に感じることもあるようです。
また、すららは無学年式のため、子どもが自分に合ったレベルを選んで学習できるのが魅力ですが、「どこから手をつけたらいいかわからない」と戸惑ってしまうケースもあります。
特に、勉強に苦手意識が強い子どもは、最初のハードルが高く感じることがあるため、親のサポートが必要になることもあります。
すららの効果を最大限に引き出すためには、「子どもがどれくらい自主的に取り組めるか?」を考えたうえで導入することが大切です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
家庭用タブレット教材「すらら」は、対話型学習や無学年学習、すららコーチのサポートなど、他の学習教材にはない特徴を持っています。
しかし、その分料金もやや高めに設定されており、「すららは高いのでは?」と感じる方もいるかもしれません。
そこで、すららの料金プランについて詳しく紹介します。
入学金や月額料金、コースごとの違いを確認し、自分に合ったプランを選ぶ際の参考にしてください。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららを利用するには、月額料金のほかに入学金がかかります。
コースによって入学金が異なるので、以下の表で確認しておきましょう。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららの3教科コース(国語・数学・英語)の料金プランは、毎月支払いと4ヵ月継続コースの2種類があります。
長期利用を前提とする4ヵ月継続コースの方が、月額料金が少しお得になります。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
すららの4教科コース(国語・数学・理科・社会)は、小学コースと小中コースでプランが分かれています。
こちらも、毎月支払いと4ヵ月継続コースが選べます。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
すららの5教科コース(国語・数学・理科・社会・英語)は、最も充実した学習プランです。
5教科を学ぶため、料金は他のコースよりもやや高めですが、しっかりとした学習サポートを受けることができます。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
すららの料金は、他のタブレット教材と比較するとやや高めに感じるかもしれません。
しかし、その分「無学年学習」「すららコーチによるサポート」「AIを活用した学習設計」など、他の教材にはないメリットがあります。
特に、個別指導の塾に通うことを考えた場合、すららの月額料金は比較的リーズナブルです。
例えば、一般的な個別指導塾では1教科あたり月10,000円以上かかることもありますが、すららなら5教科学んでも約10,000円で済みます。
また、1契約で兄弟が一緒に利用できるため、複数の子どもがいる家庭ではコスパがさらに良くなります。
単なる料金の安さだけでなく、「どのような学習サポートを求めるか?」を考えて、選ぶことが大切です。
すららは、対話型授業や無学年学習、AIサポートなど、他のタブレット教材にはない強みがあります。
その分、料金はやや高めですが、学習環境やサポート内容を考慮すると、コストパフォーマンスは決して悪くありません。
特に、「塾には通わせたくないけど、しっかりした学習サポートが欲しい」「学校の授業だけでは不安」という家庭にはぴったりの教材です。
料金プランを理解したうえで、家庭の学習スタイルに合うかどうかを検討してみてください。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
すららは、無学年学習やAIサポートなどの独自のシステムを活用し、効率よく学習を進めることができるオンライン教材です。
特に、「自分のペースで勉強したい」「基礎からしっかり学び直したい」「定期テストの成績を上げたい」と考えている方におすすめです。
ここでは、すららの3教科コース(国語・数学・英語)がどのような勉強効果をもたらすのか、詳しく紹介します。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
すららの3教科コースでは、国語・数学・英語を重点的に学ぶことができます。
これらの科目は、学力の基礎を固めるうえで非常に重要であり、中学生の場合は内申点にも直結するため、特にしっかりと学習しておきたい科目です。
すららの独自システムを活用することで、短時間で効果的に学習を進められるのが特徴です。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららは、「無学年学習」という特徴を活かし、学年に関係なく基礎から学習できるため、「わからないまま進んでしまう」ことがありません。
例えば、数学でつまずいている場合、小学校の範囲までさかのぼって復習し、基礎をしっかり固めたうえで次に進むことができます。
この仕組みのおかげで、「なんとなく理解している」ではなく、「しっかりと理解し、確実に解ける」状態を短期間で作ることができます。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
すららの学習は、単に「問題を解くだけ」ではなく、解説を通じて「なぜそうなるのか?」を理解し、その後に応用問題に取り組む流れができています。
例えば、英語の学習では「単語や文法を学ぶ→簡単な例文で実践→長文問題で応用」という形で、段階的に力をつけていけます。
数学では「基本的な計算問題→考え方の解説→応用問題」といったステップが組まれており、理解が深まるごとに少しずつ難易度が上がるため、無理なく力を伸ばしていくことが可能です。
この「できる→わかる→応用」というサイクルを短時間で繰り返せることで、学習効果を最大化できるのがすららの強みです。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生にとって、国語・数学・英語の3教科は内申点を左右する重要な科目です。
特に数学と英語は、「苦手科目になりやすい」「得点差が出やすい」科目のため、ここでしっかり点数を取れるかどうかが、受験の結果にも影響を与えます。
すららでは、定期テスト対策として、頻出問題や応用問題にも対応した学習ができるため、「定期テストで点数を上げたい」「通知表の評価を上げたい」という目的に直結する学習が可能です。
また、学習履歴がデータとして残るため、「どこが苦手なのか?」をAIが分析し、重点的に学ぶべき単元をピックアップしてくれるのも大きなメリットです。
こうしたシステムのおかげで、「何を勉強すればいいかわからない…」という状況を防ぎ、効率よく成績を上げることができます。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
すららの4教科コースでは、国語・数学・英語に加えて、理科または社会のいずれかを学ぶことができます。
理科・社会は暗記が多く、定期テストや受験のためにしっかり対策が必要な科目です。
すららの学習システムを活用することで、効率よく理解を深め、テスト対策を進めることができます。
ここでは、すらら4教科コースの具体的な勉強効果について紹介します。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理科や社会は、「一度覚えたつもりでも、しばらくすると忘れてしまう」ということがよくあります。
すららでは、繰り返し学習と確認テストを組み合わせることで、知識の定着率を高める仕組みが整っています。
たとえば、理科の生物分野では、「植物の構造」を学んだ後に小テストを行い、一定の期間が空いた後に再度復習することで、長期記憶として定着しやすくなります。
社会の歴史分野でも、「流れを理解→確認問題でアウトプット→再確認」といった学習サイクルを繰り返すことで、知識を確実に定着させることができます。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
すららの理科・社会は、「とにかく暗記しなければならない」というわけではなく、重要なポイントを絞って効率よく学習できるように設計されています。
たとえば、地理の学習では「気候・地形ごとの特徴」をアニメーションで視覚的に理解できるため、単なる暗記ではなく、イメージとして記憶に残りやすくなります。
また、理科の化学分野では、実験の様子を動画で確認しながら学べるため、教科書だけでは理解しにくい内容もスムーズに理解できます。
このように、すららでは「必要な知識を短時間で効率よく学ぶ」ことができるため、限られた時間の中で最大の学習効果を得られます。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
塾や学校の授業では、決められた時間内に進めるため、「理解できなくても次に進まざるを得ない」ことがあります。
しかし、すららでは、苦手な単元はじっくり復習し、得意な単元は効率よく進めることができるため、学習の自由度が高いのが特徴です。
また、テスト対策として「間違えた問題を重点的に復習」「理解不足の単元をAIが自動で分析し、必要な問題を出題」といった機能があるため、短時間で効率よく試験対策が可能です。
特に、定期テスト前に「どこを重点的に勉強すればいいのかわからない」という子どもにとっては、的確な指示をもらいながら学習できるのは大きなメリットです。
学校の授業や塾と併用することで、より効果的なテスト対策ができるでしょう。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
すららの5教科コースでは、国語・数学・英語・理科・社会のすべてを学習できます。
中学生にとって、主要5教科のバランスを取ることは内申点の向上に直結し、高校受験においても大きなメリットとなります。
また、AIによる個別最適化学習ができるため、苦手分野を重点的に克服しながら、効率よく成績アップを目指せます。
ここでは、すらら5教科コースの具体的な勉強効果について詳しく紹介します。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結 / 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学生の通知表(内申点)は、定期テストの点数だけでなく、5教科のバランスが重要です。
すららの5教科コースを活用することで、主要科目を偏りなく学習でき、内申点の向上につなげることができます。
特に、苦手な教科があると内申点に大きく影響するため、「数学は得意だけど国語が苦手」「理科と社会の勉強の仕方がわからない」といった場合でも、すららならAIが自動で苦手を分析し、効率的に学習を進められます。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ / 模試や過去問対策にも応用できる
高校受験では、学校の定期テストだけでなく、模試や過去問演習を通じた実力強化が求められます。
すららの5教科コースでは、基本から応用まで体系的に学習できるため、受験対策としても非常に効果的です。
特に、理科や社会は暗記だけではなく、応用問題の演習を積み重ねることが大切です。
すららでは、重要ポイントを押さえながら効率よく学習できるため、受験本番で必要な「考える力」も鍛えることができます。
また、AIが苦手分野を特定し、自動で復習問題を出してくれるため、効率よく得点力を向上させることが可能です。
勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
すららの大きな特徴の一つが、AIによる個別最適化学習です。
すららでは、学習の進捗や理解度をAIが自動で分析し、必要な問題を適切なタイミングで出題してくれます。
「どの教科のどの単元が苦手なのか」「どこを重点的に復習すればいいのか」が明確になるため、無駄のない学習が可能です。
また、AIが自動で学習計画を作成してくれるため、「何をどの順番で勉強すればいいのかわからない」といった悩みを解決してくれます。
特に、効率よく勉強したい子どもや、学習習慣がまだ定着していない子どもにとって、大きなメリットになります。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
すららの5教科コースを利用している人の中には、「他の教材や塾と比べて、短時間で多くの内容を理解できる」と感じる人が多いです。
学校の授業や塾では、カリキュラムが固定されているため、理解できなくても次に進まざるを得ないことがあります。
しかし、すららなら、自分のペースで学習でき、苦手な部分は何度でも復習できるため、理解度が格段に上がります。
また、アニメーションや視覚的な解説を活用することで、教科書の内容をより深く理解しやすくなっています。
「勉強時間は限られているけれど、しっかり成果を出したい」という人には、すららの5教科コースは非常に効果的な学習方法と言えるでしょう。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
すららは、発達障害や不登校の子どもたちにも対応したオンライン学習教材として、多くの家庭で活用されています。
学校の授業についていけない、対人コミュニケーションが苦手、決まったペースで学習を進めるのが難しいといった悩みを持つ子どもでも、自分のペースで無理なく学べるのが特徴です。
ここでは、すららが発達障害や不登校の子どもにとって「安心・安全な学習環境」である理由について詳しく紹介します。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
学校の授業は、決められたカリキュラムに沿って進められるため、一度遅れると追いつくのが難しくなり、ストレスを感じることがあります。
しかし、すららでは学年に関係なく、自分の理解度に応じて自由に学習できるため、プレッシャーを感じることなくマイペースに勉強を進めることができます。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
すららは無学年式の学習システムを採用しているため、苦手な単元に戻って復習したり、得意な科目を先取りしたりすることが可能です。
学校の授業についていけない不安や、「決められたペースで進まなければならない」というプレッシャーがなくなるため、安心して学習を続けられます。
特に、不登校の子どもにとっては、学校の授業の進度を気にせず、自分に合ったペースで学べることが大きなメリットとなります。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
発達障害の子どもは、それぞれ特性が異なります。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもは、集中力が続きにくいため、短時間で効率よく学習できる環境が求められます。
一方で、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、ルーティンを大切にする傾向があるため、決まった時間に決まった学習をすることで安心感を得られます。
すららでは、ADHDの子どもは「集中できるときに一気に学習」、ASDの子どもは「毎日決まったペースで学習」といったように、それぞれの特性に合わせた学習スタイルを実現できます。
このように、自分に合った学習ペースを選べることが、すららの大きな強みです。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
人とのコミュニケーションに不安を感じる子どもにとって、対面の授業や塾は大きなストレスになることがあります。
すららでは、アニメーションのキャラクターが先生役となり、優しくわかりやすく教えてくれるため、対面でのやり取りが苦手な子どもでも安心して学習を進めることができます。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
すららでは、アニメーションのキャラクターが授業を進めてくれるため、先生やクラスメイトの目を気にすることなく、リラックスして学習できます。
また、間違えても感情的なフィードバックを受けることがないため、「怒られるのが怖い」「間違うのが恥ずかしい」といった不安を抱えることなく、落ち着いて取り組めるのが特徴です。
特に、発達障害の子どもは「人の表情や態度を敏感に感じ取る」「怒られることが苦手」という特性を持つことがあるため、感情的なプレッシャーを受けずに学べる環境は非常に重要です。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
学校や塾では、先生やクラスメイトとの関わりが避けられないため、対人関係が苦手な子どもにとっては、それ自体が学習のハードルになってしまうことがあります。
すららは、完全にオンラインで学習できるため、対人関係のストレスを感じることなく、安心して勉強に集中することができます。
また、すららには「すららコーチ」というサポート制度があり、必要なときにだけアドバイスを受けることができるため、必要以上のコミュニケーションを強制されることもありません。
これにより、無理なく自分のペースで学習を続けることができます。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは、発達障害のある子どもでも安心して学べるように、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れて設計されています。
これは、「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」学習環境を提供することを目的としており、学習の苦手さを感じる子どもでも無理なく学べる工夫がされています。
特に、読字障害(ディスレクシア)や言語理解に時間がかかる子ども、視覚・聴覚のどちらの情報処理が得意かによって学習スタイルが異なる子どもに対応できる仕組みが整っているのが特徴です。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
すららの教材は、単なる文字や音声による学習ではなく、視覚・聴覚の両方を活用しながら学べる構成になっています。
アニメーションを用いた授業や、音声解説、要点をまとめたテキスト表示など、さまざまな形式で情報を伝えることで、学習のハードルを下げています。
また、学習の進め方もシンプルでわかりやすく、次に何をすればいいのかが明確になっているため、「どこから手をつければいいかわからない」という不安が少なくなります。
こうした設計により、学習の苦手な子どもでもスムーズに学びを進めることができます。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
読字障害(ディスレクシア)の子どもは、文字を読むことに苦手意識を持っていることが多いため、文章だけの教材では理解が進みにくいことがあります。
すららでは、音声での説明や、図・アニメーションを活用した解説が多く取り入れられているため、文字を読むのが苦手な子どもでも、直感的に学習内容を理解しやすくなっています。
また、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、言葉の意味を正確に理解するのに時間がかかることがありますが、すららでは、具体的な例を交えながらわかりやすく説明してくれるため、理解をサポートしてくれます。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
発達障害の子どもには、「視覚優位」と「聴覚優位」の学習タイプがあります。
視覚優位の子どもは、図や文字、イラストを活用した学習の方が理解しやすく、聴覚優位の子どもは、音声で説明を聞くことで学習が進めやすい傾向があります。
すららでは、視覚的なアニメーションと音声解説の両方が組み合わされているため、どちらのタイプの子どもにも適した学習環境が提供されています。
また、アニメーションのキャラクターが会話形式で進める授業は、視覚と聴覚の両方をバランスよく使いながら学べるため、学習効果が高まりやすいのも特徴です。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
すららには、音声の速度を調整できる機能が搭載されており、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」といった子どもそれぞれのニーズに応じた学習が可能です。
たとえば、言葉の理解に時間がかかる子どもは、音声をゆっくり再生することで、ひとつひとつの説明をじっくり聞くことができます。
一方で、テンポよく学習を進めたい子どもは、音声を速くすることで効率よく学ぶことができます。
このように、子ども一人ひとりの特性に応じて学習環境を調整できるのが、すららの大きな強みです。
すららは、発達障害のある子どもにも対応したユニバーサルデザインを取り入れることで、学習のつまずきを減らし、誰でもスムーズに学べる環境を整えています。
視覚・聴覚のどちらの学習タイプにも適応できる教材設計や、学習ペースを調整できる機能があることで、一人ひとりに合った学び方ができるのが魅力です。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
すららは、間違えることに対してネガティブな感情を持たせない設計になっています。
学校や塾では、授業中に間違えると「恥ずかしい」「できない自分を責めてしまう」といった気持ちになりがちですが、すららではそのようなストレスを感じることなく学習できます。
特に、発達障害のある子どもは、「間違えることへの不安」や「失敗への過剰な反応」を持ちやすい傾向がありますが、すららの学習システムなら、安心して学び続けることができます。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららでは、問題を間違えたときに、単に「不正解」と表示されるのではなく、「なぜ間違えたのか」「どうすれば正しく解けるのか」を丁寧に説明してくれます。
間違えたことを否定されるのではなく、「次はこうすればいいんだ」と納得できる解説があるため、自己肯定感を下げることなく学習を続けられます。
これにより、「間違えてもいい」「学び直せば大丈夫」という前向きな気持ちで取り組むことができるようになります。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
学校や塾では、クラスメイトの前で答えを間違えたり、先生に指摘されたりすると、「恥ずかしい」「できない自分が嫌になる」と感じる子どももいます。
特に、発達障害のある子どもは、「できないことを指摘されるのが怖い」「人前で間違えるのが嫌」といった気持ちから、勉強そのものが苦手になってしまうこともあります。
しかし、すららは個別学習スタイルなので、他人の目を気にせず、自分のペースで学習できます。
間違えても、誰かに指摘されることなく、冷静に解説を聞いて理解を深めることができるため、ネガティブな感情を抱くことが少なくなります。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
すららは、学習を単なる「勉強」ではなく、「楽しい体験」として続けられるように設計されています。
学習の途中でアニメキャラクターがナビゲートしてくれたり、クイズ形式の問題が出されたりするため、遊びながら学べる感覚になります。
特に、飽きっぽい子どもや、集中力が続きにくい子どもにとって、「もっとやりたい」「もう少し進めてみよう」と思わせる工夫がされているのが特徴です。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
すららの授業は、単調な解説ではなく、アニメキャラクターが会話形式で進行するため、まるでストーリーを楽しんでいるような感覚で学習できます。
また、クイズ形式の問題や、選択肢を選ぶことでストーリーが進んでいくような演出もあるため、「あと少しだけやってみよう」という気持ちになりやすくなっています。
「次の問題を解けば、キャラが褒めてくれる」「ストーリーが進む」といった要素があることで、学習に対するモチベーションを維持しやすいのがポイントです。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもは、長時間の学習が苦手であったり、興味が移りやすかったりするため、「すぐに結果が出る」「すぐにフィードバックがある」ことが重要になります。
すららでは、問題を解くたびに「正解!」「惜しいね!」といったフィードバックがあり、すぐに結果がわかるため、やる気を維持しやすくなります。
また、短い時間で達成感を得られる仕組みになっているため、「あと1問だけ」「もう少し進めてみよう」と思いやすくなり、結果的に学習の継続につながります。
すららは、学習に対するネガティブな感情を減らし、楽しく続けられる仕組みが整っています。
「勉強=つまらない」「間違えたら怒られる」といったストレスがなく、自己肯定感を保ちながら学べるので、学習に対するハードルを下げてくれるのが特徴です。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
すららには「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの専門家がついており、子ども一人ひとりに合った学習計画の作成や、つまずきポイントの分析をしてくれます。
特に、発達障害のある子どもを持つ家庭では、「どのように勉強を進めればいいかわからない」「親がすべてサポートするのは大変」といった悩みを抱えることが多いですが、すららコーチのサポートがあることで、親子で抱え込まずに学習を進めることができます。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららコーチの多くは、ADHD(注意欠陥・多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)、学習障害(LD)などの特性を理解し、それに合わせた学習支援を行っています。
例えば、ADHDの子どもには「短時間で集中できる学習スタイル」を提案したり、ASDの子どもには「ルールや手順を明確にした計画」を立てたりすることで、無理なく学習を続けられるようサポートします。
また、学習障害のある子どもには、「文章を読むのが苦手なら音声学習をメインに」「計算が苦手なら視覚的なサポートを活用する」など、個々の特性に合わせた学習方法を提案してくれるため、子どもがつまずかずに前に進むことができます。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
すららコーチは、子どもの学習進度を分析し、最適な学習計画を立ててくれるため、「どこから手をつけたらいいのかわからない」という悩みを解消できます。
特に、発達障害のある子どもは、自分で計画を立てたり、学習のペースを管理するのが難しいことがありますが、すららコーチが適切なペース配分を考えてくれるので、無理なく学習を継続できます。
また、つまずきやすいポイントを把握し、「どこで苦戦しているのか」「どうすれば克服できるのか」を具体的に教えてくれるため、効率的に苦手を克服できるのも大きなメリットです。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
すららは、完全オンラインの学習教材なので、通塾の必要がなく、家にいながらすべての学習を完結できます。
不登校の子どもや、外出が難しい子どもにとって、無理に学校や塾に通う必要がないのは大きな安心材料です。
また、親の送迎負担がなくなるため、忙しい家庭でも取り入れやすいのが特徴です。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
すららは、タブレットやPCが1台あればすぐに学習を始められるため、特別な準備が必要ありません。
一般的な通信教育では、教材の管理や、親が学習のサポートをする必要がある場合が多いですが、すららなら教材の整理やプリントの用意をする必要がなく、親の負担が大幅に軽減されます。
また、学習進捗の管理もオンライン上で完結するため、「今日はどこまで進めたのか」「どの分野が苦手なのか」がすぐに確認でき、無駄なく学習を進められます。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
不登校や、病気・ケガなどで一時的に学校に通えない子どもにとって、学習の遅れは大きな不安要素になります。
しかし、すららなら、学校の授業と関係なく自分のペースで学べるため、「学校に行けない間も勉強を進められる」という安心感があります。
また、無学年式の学習システムを採用しているため、必要に応じて過去の内容を復習したり、逆に先取り学習を進めたりすることも可能です。
こうした柔軟な学習スタイルにより、「学校に行けなくても大丈夫」という自信を持たせてあげることができます。
すららは、完全オンラインで学習を完結できるため、通塾の負担がなく、親子ともにストレスなく勉強を続けられます。
また、学習の遅れを取り戻しながら自信を育てることができるため、不登校や発達障害のある子どもにとって、安心して学べる環境が整っています。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
すららは、無学年式の学習システムやすららコーチのサポートが特徴の家庭用タブレット教材ですが、利用をやめたい場合、どのような手続きが必要なのか気になる方もいるかもしれません。
特に、「解約」と「退会」の違いや、手続きをスムーズに進めるためのポイントを知っておくことは重要です。
ここでは、すららの解約・退会方法について詳しく紹介します。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
すららをやめる場合、「解約」と「退会」の2つの方法がありますが、それぞれの意味が異なります。
間違った手続きをしないためにも、違いをしっかり理解しておきましょう。
すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
「解約」は、すららの利用を一時的に停止する手続きのことを指します。
解約手続きを行うと、毎月の支払いが止まり、すららの学習コンテンツにアクセスできなくなります。
ただし、解約後もすららの会員情報自体は残るため、再度利用を再開することが可能です。
例えば、「受験が終わったから一旦休止する」「しばらく学習を中断するが、また利用する可能性がある」といった場合には、解約を選ぶのが適しています。
すららの退会は「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。
「退会」は、すららの会員情報を完全に削除する手続きのことを指します。
退会手続きを行うと、すららの学習履歴や個人情報が削除され、今後すららを利用する際には新規登録が必要になります。
つまり、一度退会すると、これまでの学習記録を復元することができなくなるため、「もう二度と利用するつもりがない」「完全にやめたい」という場合のみ、退会を選ぶのがよいでしょう。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららの解約手続きは、WEBやメールでは受け付けておらず、必ず電話で行う必要があります。
解約を希望する場合は、すららコール(サポートセンター)に直接連絡し、手続きを進めてください。
| 【すららコール】 0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
すららの解約は、WEBサイトやメールでは手続きができず、必ず電話で行う必要があります。
これは、本人確認を確実に行うための措置と考えられます。
メールやWEBで簡単に解約できない点は少し手間に感じるかもしれませんが、電話一本で解約手続きを完了できるため、手続き自体はシンプルです。
解約を考えている場合は、サポートセンターの受付時間内に電話をするようにしましょう。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
すららの解約手続きを進める際には、電話で本人確認が必要になります。
電話をかける際には、以下の情報を準備しておくとスムーズに手続きが進みます。
– 契約者の氏名
– すららの登録ID(会員番号)
– 登録している電話番号
オペレーターから本人確認のためにこれらの情報を求められるため、事前に準備しておくとスムーズです。
特に、登録IDは普段あまり意識しない情報かもしれませんが、マイページなどで確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
解約手続きを進める際には、「いつ解約するか」を決めておく必要があります。
すららでは、解約時の日割り計算がないため、月の途中で解約しても、その月の利用料は全額発生します。
そのため、月末に解約するのか、次の支払いが発生する前に解約するのかをしっかり考えておくことが重要です。
例えば、「来月からすららを利用しない予定だけど、今月の途中で解約したら損をする?」と気になる場合は、サポートセンターに問い合わせて、最適な解約タイミングを相談するのもよいでしょう。
すららの解約は、電話一本で手続きが可能ですが、解約と退会の違いを理解した上で、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
また、解約時には本人確認が必要になるため、事前に登録情報を確認しておくとスムーズに進みます。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららを完全に退会したい場合は、解約手続きを完了した後に、退会の依頼を行う必要があります。
解約だけでは、アカウントや学習データが残るため、「もう二度と使わない」「個人情報を削除してほしい」といった場合にのみ、退会の手続きをするのが適しています。
一方で、「また再開するかもしれない」という場合は、解約のみで問題ありません。
ここでは、すららの退会手続きの方法について詳しく解説します。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
すららの退会は、解約と同じく「すららコール(サポートセンター)」に電話をして依頼する必要があります。
退会を希望する場合は、解約の手続きが完了したタイミングで「退会も希望します」と伝えましょう。
オペレーターに退会の意思を伝えると、アカウントの削除手続きが進められます。
退会手続きが完了すると、学習履歴や登録情報が完全に削除され、今後すららを利用したくなった場合でも、新規登録が必要になります。
そのため、「本当に退会してしまってよいのか?」を事前にしっかり考えてから依頼することが大切です。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
すららの解約手続きを済ませると、月額料金の支払いは停止されます。
そのため、解約だけで問題ない場合は、無理に退会をする必要はありません。
例えば、「しばらく使わないけど、また利用するかもしれない」「学習データを残しておきたい」という場合は、退会せずにアカウントを残しておくのがベストです。
すららの退会は、「完全にアカウントを削除したいとき」にのみ行う手続きです。
解約をして料金の支払いが止まれば、それ以上の費用が発生することはないため、焦って退会する必要はありません。
今後の利用の可能性を考えながら、最適な選択をするのがおすすめです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
すららは、無学年式の学習ができる家庭用タブレット教材ですが、「どう使えば一番効果的なの?」と悩む方もいるかもしれません。
特に、小学生は学習習慣がまだ身についていないことが多いため、使い方によっては継続できなかったり、効果を実感しにくかったりすることもあります。
そこで、すららを最大限活用するための効果的な使い方について、小学生向けに詳しく紹介します。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生がすららを使う際には、「無理なく続けられること」が何より大切です。
大人が思うよりも、子どもにとって「勉強を続ける」というのはハードルが高いものです。
そこで、習慣化しやすい方法を取り入れたり、モチベーションを維持できる工夫をすることで、学習の効果を最大限引き出すことができます。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
すららを効果的に活用するためには、「短時間でもいいから毎日取り組む」ことがポイントです。
特に小学生は集中力が長く続かないことが多いため、1回の学習時間を短めに設定し、できるだけ毎日続けることが重要です。
目安としては、1回20〜30分程度が理想的です。
「今日は1時間やろう!」と意気込むよりも、「毎日20分だけ」と決めたほうが、学習の習慣化につながります。
また、すららのレッスンは1ユニットごとに区切られているため、「今日は1ユニットだけ」と決めるのもよいでしょう。
毎日の学習リズムを作ることで、無理なく続けることができます。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
子どもが学習を続けるためには、「達成感を感じられる仕組み」がとても大切です。
特に、小学生は「やる気スイッチ」が目に見える形であると、モチベーションを維持しやすくなります。
例えば、「1ユニット終わったらシールを貼る」「5回学習したら好きなおやつを選べる」といった、ごほうび制度を作るのも効果的です。
こうした小さな成功体験を積み重ねることで、「次もやってみよう!」という気持ちになり、学習が継続しやすくなります。
すらら自体もクイズ形式の要素があるため、ゲーム感覚で楽しめる部分はありますが、さらに「親からのごほうび」などを組み合わせると、より効果的に学習を続けることができます。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
低学年の子どもは、「勉強をひとりでする」という習慣がまだ定着していないことが多いため、最初のうちは親も一緒に取り組むと効果的です。
「今日はどんな問題を解いたの?」「ちょっと一緒にやってみよう!」といった声かけをすると、子どもは勉強を「楽しいこと」と認識しやすくなります。
特に、すららはアニメーションキャラクターと対話しながら進める学習スタイルなので、「どんなふうに説明してくれるのか親も見てみる!」という姿勢を見せると、子どもも「ママ・パパと一緒ならやってみよう!」という気持ちになりやすいです。
低学年のうちは「自分だけでやるより、親と一緒のほうが楽しい」と感じることが多いため、まずは親が寄り添いながら学習を進めるのがポイントです。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/ 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
子どもは得意な科目ばかりをやりがちですが、学習の効果を最大限に引き出すためには、苦手な部分を重点的に学ぶのが重要です。
すららにはAI診断機能があり、どこでつまずいているのかを分析することができるため、「苦手な単元からスタートする」という使い方がおすすめです。
例えば、「算数の割り算が苦手」といった場合、すららの診断結果をもとに、その部分を重点的に学習することができます。
また、「国語の読解問題が苦手」という場合は、文章の意味を理解するトレーニングを取り入れることも可能です。
AIが分析してくれるので、親が「どこが苦手なのか?」を探る手間が省けるのもメリットです。
すららの効果的な使い方として、「短時間で毎日学習する」「ごほうび制度でやる気を引き出す」「親も一緒に楽しむ」「苦手克服から始める」といったポイントを押さえておくと、無理なく継続しやすくなります。
特に小学生のうちは、学習習慣を身につけることが何よりも大切なので、楽しみながら続けられる環境を整えてあげるのがポイントです。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、定期テストや高校受験を意識した学習が必要になります。
また、部活や習い事で忙しく、勉強時間の確保が難しくなることもあります。
そんな中でも、すららを上手に活用すれば、効率的に学習を進めることができます。
ここでは、中学生がすららを最大限活用するための効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
中学生にとって、定期テストは内申点に直結する重要な試験です。
すららでは、単元ごとにまとめテストが用意されているため、定期テストの範囲を逆算して学習計画を立てると効果的です。
まず、学校のテスト範囲を確認し、「どの単元をどれくらい学習する必要があるのか」を整理しましょう。
そして、すららのAI診断機能を活用し、苦手な分野を重点的に学習することで、効率よく得点力を上げることができます。
特に数学や英語は、基礎が固まっていないと応用問題が解けないため、「苦手なところをつぶす」という意識を持つと、テストでの点数アップにつながります。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
中学生は、部活や学校行事で忙しく、勉強時間が不規則になりがちです。
そこでおすすめなのが、「寝る前のタブレット学習ルーティン」を作ることです。
例えば、「部活から帰って夕食を食べた後に、すららを30分だけやる」「寝る前に英語のリスニングを10分聞く」といったように、決まった時間に取り組むことで、学習のペースを乱さずに続けることができます。
すららはスマホやタブレットで手軽に学習できるため、机に向かうのが億劫なときでも、ベッドの上やリラックスした環境で取り組むことができるのもメリットです。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
すららには、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポート機能があり、学習計画の作成や、つまずいたときのアドバイスをしてくれます。
中学生になると、勉強の範囲が広くなり、「どこから手をつけたらいいかわからない」と感じることが増えてきます。
そんなとき、すららコーチを活用すれば、自分に合った学習プランを立ててもらうことができるので、計画的に学習を進められます。
また、「やる気が出ない」「モチベーションが続かない」という場合も、すららコーチに相談することで、学習のアドバイスをもらうことができます。
一人で勉強するのが難しいと感じたときは、積極的に活用してみましょう。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
中学生の学習では、「復習」と「予習」のバランスが重要になります。
すららを活用すれば、学校の授業に合わせた予習・復習がスムーズに行えます。
特に、英語や数学は、授業の前に予習をしておくと理解しやすくなります。
例えば、英語の文法や単語を事前に学んでおけば、授業で「知っている内容」として聞けるため、より深く理解することができます。
また、数学の公式も、先に覚えておくことで、学校の授業で「どのように使うのか」を意識しながら学ぶことができるようになります。
一方で、国語や社会、理科のように「知識を定着させること」が大切な科目は、授業の後に復習をするほうが効果的です。
すららのAI診断を活用し、「どこが理解できていないのか」をチェックしながら、重点的に復習することで、定期テストや受験対策につなげることができます。
すららは、中学生の学習スタイルに合わせて柔軟に活用できるのが特徴です。
定期テスト対策として計画的に学習を進めること、部活との両立を考えたルーティンを作ること、すららコーチを活用して学習を効率化すること、そして予習と復習のバランスを取ることが、効果的な活用方法になります。
無理なく継続できる方法を見つけ、自分に合ったスタイルで学習を進めていきましょう。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、学習内容が一気に難しくなり、学校の授業だけでは理解が追いつかないことも増えてきます。
また、大学受験を視野に入れると、自分のペースでしっかり学習を進めることが重要になります。
すららは、苦手克服や受験対策にも活用できるため、高校生にとっても効果的な学習ツールになります。
ここでは、高校生向けのすららの効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校の勉強では、苦手な部分を放置すると授業についていけなくなり、学習全体が苦しくなってしまうことがあります。
すららでは、無学年式の学習システムを活用して、苦手な単元を基礎からしっかり復習することができます。
例えば、数学の関数が苦手な場合は、中学数学の「比例・反比例」「一次関数」などの基礎から学び直すことで、スムーズに高校レベルの内容に取り組めるようになります。
一方、得意な分野については、すららの応用問題にチャレンジし、発展的な学習を進めることができます。
「苦手克服」と「得意分野の強化」をバランスよく進めることで、効率的に学力を伸ばすことができます。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
高校の授業は、先生の進め方や学校のカリキュラムによって、自分に合わないと感じることもあります。
「授業のスピードが速すぎてついていけない」「逆に、もっと先の内容を学びたいのに進みが遅い」といった悩みを抱えることもあるでしょう。
そんなとき、すららを活用すれば、自分の理解度に合わせたペースで学習を進めることができます。
特に、自分で学習計画を立てられるタイプの人は、すららを使って先取り学習を進めたり、授業でわからなかった部分を後からじっくり復習したりすることで、効率よく理解を深めることができます。
学校の授業に縛られずに、自分に合ったペースで学べるのは、すららの大きな強みです。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
大学受験を考える高校生にとって、模試や共通テストの対策は非常に重要です。
すららは基礎力の定着に優れているため、共通テストの基礎問題や模試の基本レベルの問題に対応する力をつけるのに最適です。
共通テストでは、「基礎をしっかり理解しているか」が問われる問題が多いため、すららを使って各教科の基礎を固めておくことで、本番での得点力を上げることができます。
また、模試の結果を分析し、「どこが弱点なのか」を把握した上で、すららの該当単元を重点的に学習することで、より効率的な対策が可能になります。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
高校生になると、勉強の計画を立てて、自分で管理する力が求められます。
すららでは、学習時間や達成度がグラフで表示されるため、「どれくらい勉強したのか」「どの分野をどれだけ学習したのか」を視覚的に把握することができます。
これにより、「今日は〇時間勉強できた」「この1週間で英語を〇時間やった」といった具体的な数値が見えるため、学習のモチベーションを維持しやすくなります。
また、学習のペースが乱れたときも、「最近、学習時間が減っているから、もう少し頑張ろう」といった調整がしやすくなります。
受験生にとっては、計画的に学習を進めるための重要なツールとなるでしょう。
すららを活用すれば、苦手分野の克服や得意科目の強化、学校の授業の補完、模試や共通テスト対策など、幅広い学習が可能になります。
特に、「基礎をしっかり固めたい」「自分のペースで学習を進めたい」という高校生には、非常に効果的な教材です。
学習の可視化機能もうまく活用しながら、効率的に勉強を進めていきましょう。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校の子どもにとって、「勉強が遅れてしまうのではないか」「生活リズムが乱れてしまう」「学校に行かなくても学習を続けられる環境がほしい」といった悩みは尽きません。
すららは、無学年式で自分のペースで学べる学習システムなので、不登校の子どもでも安心して勉強を続けることができます。
また、学習の継続をサポートする仕組みも整っているため、無理なく学習習慣をつけることが可能です。
ここでは、不登校の子ども向けのすららの効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校になると、どうしても生活リズムが乱れやすくなります。
朝起きる時間がバラバラになったり、昼夜逆転してしまったりすると、体調や気持ちの安定も難しくなります。
すららを活用すれば、「朝起きる→学習→休憩→学習」というように、簡単な「ミニ時間割」を作ることで、生活リズムを整える手助けになります。
例えば、朝9時に起きて、10時からすららで30分学習→30分休憩→もう30分学習といった形で、小さなルーティンを作ると、自然と規則正しい生活を取り戻しやすくなります。
学校に行くことが難しくても、「決まった時間に学習する習慣」をつけることで、将来的に復帰しやすくなるのもポイントです。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
学校の授業では、先生の話を聞いて、クラスメイトと一緒に学習を進めるのが一般的ですが、不登校の子どもにとっては「人と比べられる環境」がストレスになることもあります。
すららは、自宅で一人で学習を進められるため、「周りの目を気にせず、安心して勉強できる」というメリットがあります。
また、無学年式のため、自分の理解度に応じて戻り学習ができるのも強みです。
「学校の授業が進んでしまってついていけない」と焦る必要がなく、苦手な部分をゆっくり学び直すことができます。
例えば、「中学の数学が難しい」と感じたら、小学校の算数に戻って復習することも可能なので、無理なく学習を続けられます。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校の子どもは、「できないことが増えてしまった」「みんなと同じように勉強が進んでいない」という不安を抱えやすくなります。
その結果、「自信をなくしてしまう」「勉強に対するモチベーションが下がる」といった悪循環に陥ることもあります。
すららでは、学習を進めるたびに「できた!」という成功体験を積み重ねられるように設計されています。
例えば、「ユニットをクリアするとキャラクターがほめてくれる」「問題に正解すると達成感を得られる」など、小さな成功体験を積み重ねる仕組みがあります。
「少しずつでも前に進んでいる」という感覚を持つことで、自信を取り戻しやすくなります。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校の子どもは、家庭で過ごす時間が長くなるため、「親以外と話す機会が減る」「自分の悩みを誰に相談すればいいかわからない」といった孤立感を感じることがあります。
すららでは、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートスタッフがついているため、親とは違う「第三者の視点」で学習のアドバイスをもらうことができます。
例えば、「勉強がうまく進まない」「何をすればいいかわからない」といった悩みを相談すると、すららコーチが学習計画を提案してくれたり、モチベーションを上げるためのアドバイスをしてくれたりします。
親子だけで抱え込まず、第三者の存在を活用することで、精神的な負担を減らすことができます。
すららは、不登校の子どもが「無理なく学習を続けることができる」ように工夫された教材です。
生活リズムを整え、一人でも安心して学習を進められる環境を作り、成功体験を積み重ねながら自信を取り戻すことができます。
また、すららコーチのサポートを活用することで、孤立感を減らし、より前向きに学習に取り組めるようになります。
無理なく、自分のペースで続けていくことが大切です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照: 会社概要 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららというサービスに関する口コミの中には、「うざい」というワードが登場することがありますが、それがどのようにして生まれるのかについて考察してみましょう。
まず、ユーザーが「うざい」と感じる大きな要因の1つは、すららが頻繁に通知を送ることです。
これは、多くの方にとってプライベートな時間を多く要求されることと結びついています。
さらに、すららが自己主張が強いと感じられる場合も「うざい」という印象を与えかねません。
ユーザーは、自身のスケジュールやペースに合わせて利用したいと考えているため、その自由を制限されると感じることがストレスにつながるのです。
また、過剰なサポートや情報提供もユーザーが「うざい」と感じる理由の一つです。
必要以上のアドバイスやお知らせは、むしろ煩わしさを感じさせることがあります。
そのため、サービス提供側は、ユーザーのニーズや期待を的確に把握し、適切なサポートを提供することが重要です。
ユーザーの不満や批判はサービス改善の貴重なフィードバックと捉え、それを元に改善を行うことがますます重要となります。
すららがより良いユーザーエクスペリエンスを提供できるよう、運営側と利用者が協力し合い、より良い関係構築を目指していくことが必要です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららは、発達障害を抱える方々の支援を提供する専門機関として、様々なコースをご用意しております。
当施設で提供している発達障害コースの料金プランにつきまして、以下に詳細をご案内いたします。
まず、当センターで提供している発達障害コースは、個々のニーズに合わせて設計されており、従って料金もその内容や期間によって異なります。
一般的に、療法の回数や内容が増えるに従い、料金もそれに比例して調整されております。
料金プランには、通い放題や固定回数のセッションなど、お客様のご利用目的や予算に合わせて選択いただける柔軟なオプションがございます。
また、施設内でのサービスだけでなく、外部の支援機関との連携に基づいたサービスも含まれる場合がございます。
ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
すららは、皆様の発達障害へのサポートを真摯にお手伝いさせていただきます。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
不登校でお困りのご家庭にお知らせです。
すららのタブレット学習は、通学の代わりに利用いただける場合がございますが、出席扱いについては学校や教育機関によって異なります。
一般的には、学校側との調整が必要となりますので、まずは学校との相談をおすすめいたします。
すららを活用した学習が不登校の子供にとって有益であることは確かですが、出席扱いについては個々の状況により異なるため、保護者や学校とよく相談しながら進めていくことが大切です。
お子様の学びをサポートするためにも、ご家庭と学校が連携し、最善の方法を見つけることが肝要です。
不登校の子供の学びを支えるために、関係者間でのコミュニケーションを大切にしてください。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードの使い方についてご説明いたします。
当社のキャンペーンコードは、お得な特典や割引を受ける際にご活用いただける便利なものです。
キャンペーンコードをご利用いただくことで、様々なサービスや商品をお得に入手することができます。
すららのキャンペーンコードをご利用いただく手順は、非常に簡単です。
まず、お買い物や申し込み手続きを行う際に、該当するキャンペーンコードの入力欄が表示されます。
こちらに、お客様が持っているキャンペーンコードを入力していただくことで、自動的に特典が適用されます。
これにより、お支払い金額がお得になりますので、ぜひご活用ください。
また、キャンペーンコードは期間限定のものもございますので、ご利用の際には有効期限をご確認いただくことをお勧めします。
期限を過ぎると特典の適用ができなくなる場合がございますので、ご注意ください。
キャンペーンコードを利用する際は、入力する際にお間違いがないようにご注意ください。
正確なキャンペーンコードを入力いただくことで、スムーズに特典を受けられることができます。
お客様にとってより快適なお買い物体験となるよう、ご利用いただければ幸いです。
いかがでしたでしょうか。
すららのキャンペーンコードの使い方について、ご理解いただけましたでしょうか。
何かご不明点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
ますます便利にお得に利用できるよう、すららは努めて参ります。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会方法についてお知らせいたします。
すららをご利用いただき、誠にありがとうございます。
退会手続きについて大変申し訳ございませんが、以下の手順に従っていただくことで、スムーズに退会が完了いたします。
まず最初に、お客様のマイページにログインをお願いいたします。
ログイン後、画面右上にある「アカウント設定」をクリックしてください。
そこで、「アカウントの管理」や「プランの変更」の項目がございますので、そちらを選択してください。
次に、「アカウントの解約」もしくは「退会」のボタンをクリックしてください。
その後、システムが案内する手順に従い、必要事項を入力していただくことで、退会手続きが完了いたします。
退会手続きの完了後、すららのアカウントは停止され、サービスの利用ができなくなります。
ご注意ください。
一旦退会されましたら、再度ご利用いただくためには、再登録が必要になりますので、ご留意いただければと存じます。
何かご不明点やお困りのことがございましたら、お気軽に弊社のカスタマーサポートまでお問い合わせください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららを利用する際にかかる費用は、基本的には「入会金」と「毎月の受講料」です。
これ以外に追加で料金が発生することは基本的にはありません。
ただし、学習を進めるためにタブレットやPC、インターネット環境が必要となるため、これらの準備が必要になります。
また、すららでは、受講するコース(3教科・4教科・5教科)によって料金が異なります。
コースを途中で変更する場合、追加費用が発生することがありますので、事前に確認しておくと安心です。
その他、紙の教材を購入する必要はなく、すべてデジタル上で完結するため、教材費の負担はありません。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、1つの契約で兄弟一緒に利用することが可能です。
兄弟で別々のアカウントを作成し、それぞれの進度に合わせて学習を進めることができます。
追加料金なしで兄弟が利用できるため、家庭でのコストパフォーマンスが高いのが特徴です。
例えば、小学生の兄と中学生の妹がいる家庭では、同じ契約内でそれぞれの学年に合わせた学習ができるため、「兄弟で学習内容が異なるけれど、1つの契約で済むのが便利」といった声も多くあります。
ただし、兄弟で利用する場合でも、それぞれの学習データは個別に管理されるため、お互いの進捗が混ざることはありません。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語の学習が含まれています。
すららの英語は、「聞く」「読む」「話す」の3技能をバランスよく学べるカリキュラムになっており、特にリスニングや発音のトレーニングが充実しています。
また、アニメーションを活用した授業で、視覚的にも理解しやすいように工夫されています。
発音チェック機能もあり、ネイティブの発音を聞きながら自分の声を録音し、正しい発音を学ぶことができます。
英語の学習を始めるのが初めての小学生でも、無理なく取り組めるように設計されているのが特徴です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららには、「すららコーチ」という学習サポートの専門スタッフが在籍しており、受講生の学習を継続的にサポートしてくれます。
すららコーチから受けられる主なサポートは以下の通りです。
1. **学習計画のアドバイス**
すららコーチは、生徒の目標や学習状況に合わせた学習計画を提案してくれます。
特に、勉強のペースがつかみにくい人や、どこから学習を進めればよいのかわからない人にとって、適切なアドバイスを受けられるのは大きなメリットです。
2. **つまずきポイントのサポート**
AIを活用して学習の進捗や苦手分野を分析し、「どこでつまずいているのか」「どのように克服すればよいか」を具体的に指導してくれます。
苦手な部分を克服するための学習方法を教えてもらえるため、効率よく学習を進められます。
3. **保護者へのサポート**
すららコーチは、生徒だけでなく、保護者向けのサポートも行っています。
例えば、「子どもの学習の進め方がわからない」「学習のモチベーションを上げる方法を知りたい」といった保護者の悩みに対して、適切なアドバイスを提供してくれます。
4. **学習の継続サポート**
すららの学習は自宅で行うため、「続けられるか不安」「途中でやめてしまうかもしれない」といった悩みを持つこともあるでしょう。
すららコーチは、定期的に声をかけたり、学習の進捗を確認したりすることで、生徒が学習を継続しやすい環境を作ってくれます。
すららコーチは、ただの学習管理者ではなく、「一緒に学習をサポートしてくれる伴走者」のような存在です。
自宅学習でも孤独を感じることなく、安心して学び続けることができます。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
今回は、【すらら】というタブレット教材に焦点を当て、料金や口コミについて比較しました。
多くの方が気にされている「【すらら】はうざい!?」という疑問についても触れ、最悪の噂についても検証しました。
結論として、【すらら】は各学年に合わせたカリキュラムや豊富な教材が特徴であり、その効果は利用者の学習状況やニーズによって異なることが分かりました。
料金に関しては、他の教材と比較してもリーズナブルな価格帯で提供されている点も魅力の一つです。
一方で、一部の利用者からは操作性やカスタマーサポートに関する不満の声も聞かれました。
ただし、サポート体制の改善など、今後のサービス向上に期待が寄せられています。
最悪の噂についても、実際に利用したユーザーからの口コミを通して、その信憑性や根拠について検証しました。
多くの場合、クリアな誤解や誤情報が原因で広まったものであり、【すらら】自体に致命的な欠点があるという証言は少ないことが分かりました。
【すらら】を利用する際には、自身やお子さまの学習スタイルや目的に合わせて適切なプランを選択することが重要です。
また、サポートが必要な場合は運営会社に遠慮なく問い合わせることで、より効果的な利用が可能となるでしょう。
【すらら】を通じて、より充実した学習体験を享受してください。

