すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
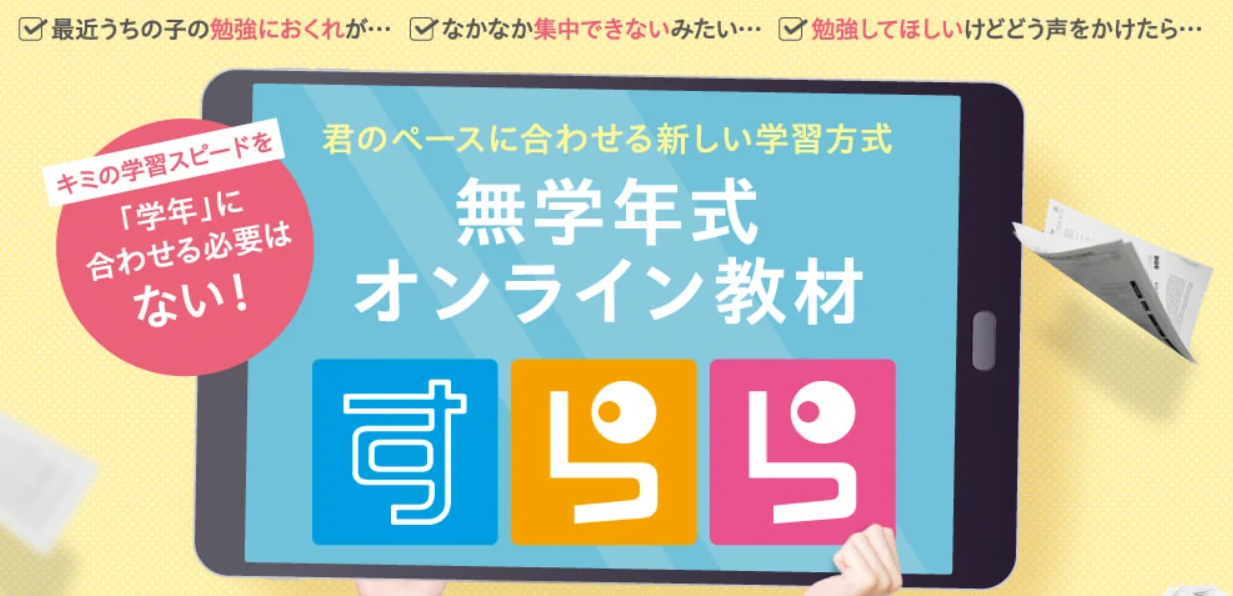
不登校の子供が家庭で学習を進める場合、「学校の出席扱いになるのかどうか」は大きな関心事のひとつです。
すららは、文部科学省の「ICTを活用した学習活動の出席扱い制度」に対応しており、条件を満たせば学校の出席日数として認められることがあります。
不登校の子供にとって、出席扱いになることで「学習の遅れを防げる」「進級や卒業に影響しにくい」といったメリットがあり、家庭学習を安心して進めることができます。
では、なぜすららが出席扱いとして認められやすいのか、その理由を詳しく解説します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、単なるオンライン教材ではなく、学習の質と学習状況の記録がしっかりと管理できるシステムを採用しています。
学校側が出席扱いと判断する際に重要なのは、「本当に学習をしているのか」という証拠を提示できることです。
すららでは、学習の進捗を自動的に記録し、学校側に提出できるレポートを作成できるため、不登校でも出席扱いとして認められやすい環境が整っています。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、子供の学習状況をシステム上で自動的に記録し、レポートとして出力することができます。
このレポートには、「どの科目をどれだけ学習したか」「どの単元を学習したか」「学習時間」などが詳しく記載されており、学校側に対して客観的な学習の証拠を提示することが可能です。
これにより、教師や教育委員会も「確かに学習が行われている」と判断しやすく、出席扱いとして認めてもらえる可能性が高くなります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
従来の家庭学習では、保護者が学習記録を手作業で管理し、学校へ報告しなければならないケースが多く、負担が大きいという課題がありました。
しかし、すららでは、学習記録が自動で保存されるため、保護者が細かく学習状況を管理する必要がありません。
さらに、学校側から見ても、データ化された学習記録は「信頼できる学習の証拠」として評価されやすいため、出席扱いとして認められるハードルが下がるメリットがあります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららが出席扱いとして認められやすいもう一つの理由は、「学習計画の明確さ」と「継続支援の充実度」にあります。
不登校の子供が自宅で学習を進める場合、「計画的に学んでいるか」「継続的に学習できているか」が重要視されます。
すららでは、専任のコーチがつくことで、学習の計画性と継続性をしっかりと学校側に示すことができます。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららには「すららコーチ」と呼ばれる専門の学習サポーターがいて、子供の学習状況をチェックしながら最適な学習計画を立ててくれます。
出席扱いとして認めてもらうためには、「単発的に学習している」のではなく、「計画的に学びを継続している」ことを学校側に示す必要があります。
すららコーチの存在により、個別に学習スケジュールを組み、進捗を管理することで、計画的に学習が進められていることを証明しやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
学習の継続は、不登校の子供にとって大きな課題の一つです。
すららでは、専任のコーチが定期的に学習の進捗をチェックし、必要に応じて学習計画を調整してくれます。
これにより、「途中で学習をやめてしまう」ということが起こりにくく、学校側に対しても「継続的な学習が行われている」とアピールしやすくなります。
コーチが適宜アドバイスをしてくれることで、モチベーションを維持しやすい環境が整っています。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららのもう一つの特徴として、「無学年式」の学習システムがあります。
これは、学年に関係なく、子供の理解度に応じて学習を進められる仕組みで、特に不登校の子供にとって大きなメリットとなります。
学校を長期間休んでいると、「どこから勉強を再開すればいいかわからない」といった問題が発生しやすいですが、すららなら、過去の単元に戻って復習したり、得意な科目をどんどん先に進めたりすることができます。
これにより、「学習の遅れを取り戻しやすい」環境が整っているため、学校側にも「無理なく学習を継続できる仕組みがある」と評価されやすくなります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
不登校の子供が出席扱いになるためには、家庭と学校の連携が欠かせません。
学校側が「家庭学習が適切に行われている」と判断するためには、学習の記録を提出することが重要です。
しかし、保護者だけでその手続きを進めるのは負担が大きく、どのように書類を用意すればいいのか迷うこともあります。
すららは、そうした保護者の負担を軽減し、学校側とのスムーズなやり取りをサポートする体制を整えています。
必要な書類の準備方法や学習レポートの提出フォロー、学校との連絡サポートなどを提供することで、家庭・学校・すららの三者での連携を実現し、出席扱いの申請をスムーズに進めることができます。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いの申請には、学校や教育委員会に対して学習状況を証明する書類を提出する必要があります。
しかし、何をどのように準備すればよいのかわからず、不安に感じる保護者も多いです。
すららでは、こうした手続きをスムーズに進めるために、必要書類の準備方法について詳しく案内してくれます。
申請に必要な情報や、どのようにまとめると学校側に理解してもらいやすいかをサポートしてくれるため、保護者の負担を大幅に軽減することができます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
学校に提出する学習レポートは、出席扱いを認めてもらうための重要な書類です。
すららでは、学習の進捗を記録し、レポートとして提出できるフォーマットを用意しています。
さらに、専任コーチがレポート作成のフォローをしてくれるため、保護者が一から作成する必要がなく、スムーズに提出することができます。
こうしたフォロー体制が整っていることで、学校側に対して「計画的な学習が行われている」ということを証明しやすくなります。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
出席扱いの申請では、学校の担任や校長との連携が重要です。
しかし、「どのタイミングで、どのように相談すればよいのか」がわからず、戸惑う保護者も多いです。
すららでは、学校とのやり取りがスムーズに進むように、相談の進め方や伝えるべきポイントについてアドバイスをしてくれます。
学校側としっかり連携をとることで、出席扱いの申請がスムーズに進みやすくなります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省の「ICTを活用した学習活動の出席扱い制度」に対応しているだけでなく、全国の教育委員会や学校と連携し、不登校支援の実績を積み重ねてきました。
多くの学校で公式に認められている学習教材であるため、学校側も導入事例を参考にしながら、出席扱いとして判断しやすいという特徴があります。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会や学校と連携しながら、不登校の子供たちの学習支援を行ってきた実績があります。
そのため、学校側も「すららを使った学習が適切なものかどうか」を判断しやすく、出席扱いとして認めるケースが増えています。
すでに他の自治体や学校で出席扱いになった実績があることで、新たに申請する際にもスムーズに話を進めやすくなります。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省が推奨する「不登校支援教材」として、多くの学校で導入されています。
これは、単なるオンライン学習教材ではなく、学校教育の補完として機能する仕組みが整っていることの証明でもあります。
学校側にとっても、すららを活用することで、不登校の子供の学習状況を把握しやすくなるため、出席扱いとして認められやすくなっています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いとして認められるためには、家庭学習の環境が「学校の学習環境に準じている」と判断されることが重要です。
すららは、学習指導要領に沿ったカリキュラムを採用し、学習の評価やフィードバックが行われる仕組みが整っているため、学校側にとっても安心できる学習環境とみなされやすくなっています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららのカリキュラムは、文部科学省の学習指導要領に準拠して作られています。
これにより、学校の授業と同じ内容を学ぶことができ、学習の遅れを防ぐことが可能です。
学校側も、「指導要領に沿った学習をしている」という点を確認しやすいため、出席扱いとして認められやすくなります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、学習の進捗が記録されるだけでなく、テストや確認問題を通じて学習の定着度を測る仕組みが整っています。
さらに、すららコーチが適宜フィードバックを行い、必要に応じて学習計画を調整することができます。
このように、学校の授業と同じように「学習→評価→フィードバック」というサイクルが確立されているため、学校側も家庭学習の効果を信頼しやすくなります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
不登校の子供がすららを活用して学習を進めることで、学校の「出席扱い」として認められる場合があります。
文部科学省は「ICTを活用した学習活動の出席扱い制度」を定めており、一定の条件を満たせば、オンライン学習による自宅学習も出席日数としてカウントできる仕組みになっています。
しかし、出席扱いの申請方法は学校や自治体によって異なるため、事前にしっかりと確認し、適切な手続きを進めることが重要です。
ここでは、出席扱いの申請を進めるための具体的な方法について詳しく解説します。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いの申請を行う際の最初のステップは、学校の担任や学年主任、校長先生に相談することです。
出席扱いの制度は全国共通のルールではあるものの、実際の運用は学校や自治体によって異なることがあるため、学校側の判断が大きく影響します。
そのため、まずは学校と連携を取りながら、必要な手続きについて確認することが大切です。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校側に相談する際には、出席扱いの申請に必要な書類や条件を詳しく確認しましょう。
一般的に、出席扱いの申請には以下のような要素が求められることが多いです。
・オンライン学習(すららなど)を継続的に利用していること
・学習の進捗状況を記録し、学校に提出できること
・保護者が子供の学習状況を把握し、支援していること
・学校側が「適切な学習環境である」と認めること
学校によっては、学習レポートの提出頻度や、学校との定期的な面談の実施が求められる場合もあります。
そのため、事前に学校の方針を確認し、どのような条件を満たせば出席扱いとして認められるのかを明確にしておくことが重要です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書の提出が求められる場合があります。
これは、子供の不登校が病気や精神的な負担によるものであると判断された場合、学校側が出席扱いの判断をするための参考資料とするためです。
すべてのケースで診断書が必要になるわけではありませんが、事前に学校と相談し、必要な場合は早めに準備を進めることをおすすめします。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
不登校の原因が病気や精神的ストレスに関連している場合、学校側が「医師の意見書が必要」と判断することがあります。
例えば、うつ病、不安障害、適応障害などの診断を受けている場合は、診断書を提出することで学校側の理解を得やすくなります。
一方で、単に「学校に行きたくない」「人間関係の問題で通学できない」といった理由では、診断書が不要なケースもあります。
学校によって対応が異なるため、まずは担任やスクールカウンセラーに相談し、必要書類を確認することが大切です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書や意見書を用意する際には、精神科や心療内科、小児科の医師に相談し、不登校の現状と学習の継続が必要であることを明記してもらうことがポイントです。
診断書には、以下のような内容が含まれることが望ましいです。
・子供の不登校の状態についての医師の所見
・学習を継続することが望ましいという意見
・学校復帰の可能性や、適切な学習環境についての提案
診断書があることで、学校側も「子供にとってオンライン学習が最適な選択肢である」ということを理解しやすくなり、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
ただし、診断書の発行には時間がかかることもあるため、必要になった場合は早めに医療機関を受診することをおすすめします。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いの申請を進めるうえで、学校に対して「家庭で適切な学習を続けている」という証拠を示すことが重要です。
そのため、すららの学習記録を活用し、学校側に提出することで、学習の継続性や進捗状況を客観的に証明することができます。
すららでは、学習進捗レポートをダウンロードできる機能があり、これを活用することで、保護者の手間を最小限に抑えながら、出席扱いの申請をスムーズに進めることができます。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららには、学習の進捗を記録するシステムがあり、どの科目をどの程度学習したのかが分かるレポートをダウンロードすることができます。
このレポートを活用することで、学校側に「継続的に学習している」ことを具体的なデータとして示すことが可能です。
レポートには、学習時間、学習した単元、理解度などが記録されており、これを担任の先生や校長先生に提出することで、学習の状況を正確に伝えることができます。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いの申請には、学校が正式な「出席扱い申請書」を作成する必要があります。
この申請書のフォーマットは学校によって異なりますが、一般的には以下のような情報が含まれることが多いです。
・子供の氏名、学年、クラス
・不登校の理由(必要に応じて医師の診断書を添付)
・家庭での学習環境(すららを活用した学習状況)
・学習の進捗(すららのレポートを参考に記載)
・今後の学習計画(すららコーチのサポートを受けながら進める計画など)
保護者は、申請書の作成に関して学校側と協力しながら、必要な情報を提供することが求められます。
申請がスムーズに進むように、事前に必要な書類を準備し、学校とのやり取りを円滑に行うことが大切です。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いの最終的な判断は、学校長(校長先生)が行います。
学校側が「適切な学習環境である」と認めれば、出席扱いとして承認される流れになります。
ただし、自治体や学校によっては、教育委員会の承認が必要なケースもあるため、学校と連携を取りながら、適切な手続きを進めることが重要です。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
出席扱いの判断は、基本的に校長先生が行います。
文部科学省のガイドラインでは、「校長が適切と判断すれば、オンライン学習を出席扱いとすることができる」とされています。
そのため、学習記録の提出や申請書の作成を通じて、学校側が納得できる材料を揃えることが重要です。
担任の先生と密に連携を取り、校長先生に「家庭での学習が適切に行われている」ということをしっかりと伝えることで、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、学校だけでなく、教育委員会の承認が必要な場合があります。
その場合、学校側が教育委員会に申請を行うことになるため、保護者は学校としっかり連携を取りながら、必要な書類を準備することが大切です。
すららの学習記録や学習計画を整理し、学校側と共有しながら進めることで、スムーズに手続きを完了させることができます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校の子どもにとって、「出席扱い」として認められることは、学習の遅れを防ぐだけでなく、将来の進路や精神的な安定にも大きく関わってきます。
文部科学省の指針に基づき、一定の条件を満たせば、すららなどのオンライン学習を活用することで出席日数として認められる場合があります。
出席扱いになることで、内申点の維持や学習の継続、親子双方の精神的負担の軽減といった多くのメリットが得られます。
ここでは、すららを活用して出席扱いとなることの具体的なメリットについて詳しく紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
内申点は、進学や将来の進路を考える上で非常に重要な要素の一つです。
学校では、出席日数も内申点の評価基準の一つとして考慮されるため、不登校の期間が長くなると、評価が下がる可能性があります。
しかし、すららを活用して「出席扱い」として認められることで、出席日数を確保し、内申点の低下を防ぐことができます。
これにより、将来の選択肢を広げることができるため、不登校の子どもにとって大きなメリットとなります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
内申点の評価には、学習態度や提出物の状況なども影響しますが、出席日数も大きな要素となります。
不登校の場合、授業への参加が難しくなることで出席日数が不足し、評価が下がるケースがあります。
しかし、すららを活用して学習を継続し、学校側に出席扱いとして認めてもらうことで、出席日数が確保でき、内申点の悪化を防ぐことができます。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点が下がると、希望する中学や高校への進学が難しくなることがあります。
しかし、すららを活用して出席扱いとして認められれば、内申点の維持が可能となり、進学の選択肢を狭めずに済みます。
また、学習の遅れを防ぐことで、学力試験においても不利になりにくく、より多くの進学先を検討できるようになります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校の子どもが抱える大きな悩みの一つが、「学習の遅れに対する不安」です。
「クラスの授業についていけない」「勉強が遅れてしまったらどうしよう」といった気持ちは、不登校の子どもにとって大きなストレスとなります。
すららでは、無学年式のカリキュラムを採用しており、自分のペースで学習を進めることができるため、学習の遅れを取り戻すことが可能です。
また、継続的に学習を行うことで、「もう取り戻せないのでは」という不安を軽減し、前向きに学ぶ姿勢を維持することができます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららでは、学年にとらわれず、自分の理解度に応じて学習を進めることができます。
そのため、苦手な科目を重点的に学んだり、得意な分野をさらに伸ばしたりすることが可能です。
また、AIを活用した診断機能により、「どこが理解できていないのか」を明確にし、効率的に学習を進めることができます。
これにより、学校の授業についていけないことを気にせず、安心して学習に取り組むことができます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校の子どもは、学習の遅れだけでなく、「自分は勉強ができないのではないか」「もう取り返しがつかないのでは」といった自己肯定感の低下にも直面することがあります。
すららを活用することで、自宅でも継続的に学習ができ、「自分は学び続けられている」という実感を持つことができます。
この成功体験が積み重なることで、学習に対する前向きな気持ちが生まれ、自己肯定感の低下を防ぐことにつながります。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを持つ保護者にとって、「子どもの将来への不安」や「どうサポートすればよいのか分からない」という悩みは尽きません。
特に、学習の遅れや進学に関する心配は、親にとって大きなストレスになります。
すららでは、学習の進捗を管理できるだけでなく、専任のすららコーチがサポートを行うため、親が一人で悩むことなく、安心して学習の支援を進めることができます。
また、学校とも連携をとりやすくなるため、親の負担が軽減されるのも大きなメリットです。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららでは、専任のすららコーチが子どもの学習をサポートし、家庭と学校との橋渡し役としても機能します。
学習の進捗状況をレポートとして記録できるため、学校側への説明もしやすくなります。
また、親だけが学習管理をするのではなく、すららコーチと一緒に進められるため、「どうすればいいのか分からない」と悩む必要がありません。
学校・家庭・すららの三者で協力することで、子どもの学習環境を整え、安心して学習を続けることができるようになります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
不登校の子どもが「出席扱い」として認められるためには、学校側との連携や、必要書類の準備が欠かせません。
すららは文部科学省のガイドラインに基づく教材であり、条件を満たせば出席扱いが認められる可能性がありますが、最終的な判断は学校や教育委員会に委ねられています。
そのため、申請をスムーズに進めるためには、事前に学校側と相談し、必要に応じて診断書などの書類を準備することが重要です。
ここでは、出席扱いを認めてもらうための注意点について詳しく紹介します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを申請する際に最も大切なのは、学校側の理解を得ることです。
すららは文部科学省のガイドラインに沿った学習支援ツールですが、すべての学校がその内容を詳しく知っているわけではありません。
そのため、「すららがどのような教材なのか」「どのような学習効果があるのか」を、学校側に丁寧に説明することが重要になります。
また、担任の先生だけでなく、教頭や校長にも早めに相談し、学校全体での理解を得ることが、申請をスムーズに進めるポイントとなります。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省の「ICTを活用した学習活動の出席扱い制度」に基づいて活用できる教材です。
しかし、学校側がこの制度を十分に理解していない場合、すららを使った学習を出席扱いとして認めることに不安を感じることもあります。
そのため、「すららは文科省の方針に沿った学習システムであること」「学習履歴が記録され、進捗管理ができること」を具体的に伝えることが重要です。
すららの公式サイトや、文部科学省のガイドラインを印刷して持参すると、学校側も理解しやすくなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生だけではなく、教頭や校長先生とも早い段階で話をしておくことが大切です。
学校によっては、担任の先生だけでは判断が難しく、最終的に校長先生の承認が必要になるケースもあります。
そのため、最初の相談の際に、すららの公式資料や学習レポートを持参し、学校側に理解してもらう努力をするとよいでしょう。
また、学校によっては教育委員会と連携して判断を行うこともあるため、学校側と協力しながら手続きを進めることが重要です。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、学校側から医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。
特に、不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」によるものである場合、医師の診断書が出席扱いを認めてもらうための重要な証拠となることがあります。
診断書には、「学校に通うことが困難な状況」「学習を継続することが望ましいこと」などが記載されることが多いため、医師と相談しながら、適切な内容を記載してもらうことが大切です。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
出席扱いを申請する際、学校側は「なぜ通学が難しいのか」という理由を確認することが多いです。
単なる「行きたくない」という理由ではなく、心身の健康状態が影響している場合、医師の診断書を提出することで、学校側の理解を得やすくなります。
特に、精神的な理由(不安障害・適応障害・うつ状態など)が関係している場合、診断書があることで、学校側も「オンライン学習による出席扱いが適切」と判断しやすくなります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を取得する際は、通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書をお願いしたい」と具体的に伝えることが大切です。
医師によっては、診断書の内容について具体的な指示がないと、一般的な診断書しか発行されないことがあります。
そのため、「オンライン学習を活用して学習を続けたいこと」「学校の出席扱いを申請したいこと」を事前に説明し、必要な情報を記載してもらえるようお願いするとよいでしょう。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書の内容によっては、学校側が出席扱いを認めるかどうかの判断が分かれることがあります。
そのため、診断書を書いてもらう際には、家庭での学習状況や、子どもがどのように学習に取り組んでいるかを医師に伝えることが重要です。
「すららを使って継続的に学習している」「オンライン学習によって学習意欲が維持できている」といった情報を医師に共有し、診断書にポジティブな内容を記載してもらえるようにすると、学校側の理解を得やすくなります。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いとして認められるためには、学習の内容が「単なる自習」ではなく、「学校の授業に準じたもの」である必要があります。
すららは文部科学省の学習指導要領に沿った教材ですが、学習の進め方によっては、学校側が「十分な学習が行われていない」と判断する可能性もあります。
そのため、学習時間や学習内容を意識し、学校の授業と同じレベルで取り組むことが大切です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
オンライン学習を活用した出席扱いは、文部科学省のガイドラインに基づいて認められるものですが、そのためには「学校の授業と同等の学習が行われているか」が重要になります。
すららで学習している内容が、学校のカリキュラムに沿っていることを学校側に伝え、単なる自主学習ではなく、体系的に学んでいることを示すことが求められます。
学習記録や進捗レポートを提出する際には、どの科目をどのくらい学習したのかを明確に示すことがポイントになります。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学習時間についても、学校の授業時間と極端に差があると、出席扱いとして認められにくくなることがあります。
文部科学省のガイドラインでは、具体的な学習時間の定めはありませんが、一般的には「1日2〜3時間程度」の学習時間を確保することが推奨されています。
学校側が求める基準に合わせながら、バランスよく学習を進めることが大切です。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いを認めてもらうためには、特定の科目だけを学習するのではなく、全教科をバランスよく学ぶことも重要です。
例えば、国語・数学(算数)・英語だけを重点的に学習し、理科や社会をまったく学習していない場合、学校側から「授業に準じた学習」と見なされない可能性があります。
すららでは、主要5教科を学習できるため、バランスよく進めることを意識しながら、学校側が納得できる学習計画を立てることがポイントになります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いとして認めてもらうためには、「学習状況を学校と共有し、継続的に報告すること」が求められることが多いです。
すららでは、学習の進捗を記録し、レポートをダウンロードできる機能があるため、それを活用しながら学校側と定期的にやり取りを行うことが大切です。
また、学校によっては、面談や家庭訪問を求める場合もあるため、事前にどのような対応が必要かを確認し、学校側との連携を密にしておくことが望ましいです。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
出席扱いを認めるかどうかは、最終的に学校長の判断によります。
そのため、家庭での学習状況をしっかりと学校側と共有し、「継続的に学習が行われている」ことを示すことが重要です。
すららの学習記録やレポートを活用し、定期的に学校へ報告することで、学校側の理解を得やすくなります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららでは、学習の進捗をレポートとしてダウンロードできる機能があります。
このレポートを月に1回程度、学校に提出することで、学習状況を客観的に示すことができます。
学校側に対して「学習が計画的に進んでいる」ことを伝えるためにも、定期的な提出が推奨されます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、出席扱いの判断のために、担任の先生が家庭訪問をしたり、面談を行ったりする場合があります。
こうした機会を活用し、子どもの学習状況やすららの活用方法について、具体的に説明できるように準備しておくことが大切です。
学校側の理解を得るためにも、積極的に協力する姿勢を示すことが重要です。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
学習の進捗状況をスムーズに共有するためには、担任の先生と定期的に連絡を取ることも大切です。
メールや電話などを活用し、「現在の学習状況」「次の報告のタイミング」などをこまめに伝えることで、学校側も状況を把握しやすくなります。
担任の先生が出席扱いの判断をサポートしてくれるケースも多いため、できるだけ良好な関係を築くように心がけましょう。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
出席扱いの判断は基本的に学校長が行いますが、自治体によっては教育委員会の承認が必要な場合もあります。
そのため、学校側と連携しながら、必要な手続きを進めることが大切です。
教育委員会に対しては、学校での出席扱いの判断に必要な追加資料を提出することが求められることもあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会へ申請する場合、学校側と相談しながら、どのような資料が必要かを確認することが大切です。
自治体によって求められる書類が異なることがあるため、事前に学校と話し合いながら、必要な情報を揃えておくとよいでしょう。
すららの学習レポートや、医師の診断書などが求められるケースもあるため、学校と連携しながら準備を進めることがポイントになります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
不登校の子どもがすららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、学校との円滑な連携や、学習の継続が重要になります。
すららは文部科学省のガイドラインに基づくオンライン学習教材ですが、最終的に出席扱いとして認めるかどうかは学校長の判断に委ねられています。
そのため、申請をスムーズに進めるためには、学校側の理解を得るための工夫や、子ども自身の学習意欲を示すことがポイントになります。
ここでは、すららを活用して出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを詳しく紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
すららを活用して出席扱いになった事例がすでにあることを学校側に伝えると、申請がスムーズに進む可能性が高くなります。
すららは全国の教育委員会や学校と連携し、多くの不登校の子どもが出席扱いとして認められた実績があります。
しかし、学校によっては「本当に出席扱いとして認められるのか?」と不安を感じることもあるため、他の学校での成功事例を示すことで、安心してもらいやすくなります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
すららは、すでに全国の多くの学校で「出席扱い」として認められた実績があります。
学校側に「他の学校でも出席扱いになったケースがある」ということを伝えることで、より納得してもらいやすくなります。
すららの活用実績があることを示すことで、「前例があるなら安心だ」と思ってもらえる可能性が高まります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトには、実際に出席扱いとして認められた学校の事例が掲載されています。
学校側がすららについて詳しく知らない場合は、公式サイトの情報をプリントアウトして持参し、説明するのが効果的です。
口頭で伝えるだけでなく、実際の実績を示すことで、より説得力を持たせることができます。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いを認めてもらうためには、子ども自身が学習に取り組んでいる姿勢を示すことも大切です。
学校側としては、「オンライン学習を利用するだけでなく、しっかりと勉強を続けられるのか?」という点を重視するため、本人が積極的に学習していることを伝えることで、承認を得やすくなります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
学校側に「本人がどのような気持ちで学習に取り組んでいるのか」を伝えるために、学習の感想や目標を書いたものを提出するのも効果的です。
例えば、「毎日コツコツ勉強を続けていること」「苦手科目に挑戦していること」「学習を続けることで自信がついてきたこと」などを具体的に書くと、学校側も前向きに受け止めてくれる可能性が高くなります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校によっては、出席扱いの申請に際して面談を求めることがあります。
その場合、できるだけ本人も参加し、「どのように学習しているか」「これからも続けていきたい意欲があること」を自分の言葉で伝えると、より説得力が増します。
本人が直接話すことで、「学習を継続する意思がある」と学校側が判断しやすくなり、出席扱いの申請が通りやすくなります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いとして認められるためには、「継続的に学習を行うこと」が条件となることが多いです。
そのため、最初から無理な学習計画を立てるのではなく、子どもが無理なく続けられるペースで、確実に学習を進めていくことが大切です。
すららは無学年制のため、子どもの理解度に合わせて柔軟に学習できるのが強みですが、その分、「どのくらいのペースで進めるのか」をしっかりと決めておくことが重要になります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
学校側にとって、最も重要なのは「学習が継続できるかどうか」です。
そのため、無理のない範囲で、確実に学習を進められるスケジュールを作ることが求められます。
例えば、最初は1日1時間から始めて、慣れてきたら学習時間を増やしていくなど、本人のペースに合わせて調整することが大切です。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには、学習の進め方について相談できる「すららコーチ」がいます。
学習計画を自分たちだけで考えるのが難しい場合は、コーチに相談しながら、無理なく続けられるスケジュールを立ててもらうのがおすすめです。
学校側に提出する学習計画書の作成にも役立つため、積極的に活用すると良いでしょう。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららの強みの一つは、専任のすららコーチが学習をサポートしてくれることです。
出席扱いの申請には、学習の進捗を記録し、証明することが求められる場合がありますが、その点においても、すららコーチのサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららでは、学習記録を自動で管理できるシステムが整っており、必要に応じてレポートをダウンロードすることができます。
すららコーチに相談すれば、学校側に提出するための学習レポートの準備や、学習計画の見直しなどもサポートしてもらえるため、積極的に活用すると良いでしょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららは、その独自の学習方法やコンテンツにより、一部の方々から「うざい」という口コミを受けることがあります。
このような評判が生まれる要因にはいくつかの理由が考えられます。
まず第一に、すららの学習スタイルが従来の方法とは異なる点が挙げられます。
個々の学習ペースやニーズに合わせたカスタマイズが行われるため、他の方法に慣れた方々にとっては違和感を感じることがあるかもしれません。
さらに、すららの継続的なリマインダーや定期的な問題提起は、学習者に対して一定のプレッシャーを感じさせる要素となっている可能性があります。
学習習慣の定着や成果の確認を促すための取り組みではありますが、その一環として感じられる重圧が口コミとして表れている可能性も考えられます。
総合的に考えると、すららが「うざい」という評判を受ける理由は、新しい学習スタイルや独自のアプローチにより、一部の利用者にとって違和感をもたらす要素が存在することが挙げられます。
しかし、その一方で、多くの方々がその効果や利点を享受し、前向きな評価を与えていることも事実です。
学習スタイルや感じ方は個々人によって異なるため、すべての意見を尊重しつつ、自身に合った学習方法を見つけることが重要です。
すららの利用者は、自身の学びたい目標に向かって、ポジティブな姿勢を保ちながら学習を続けていくことが大切です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららの発達障害コースの料金プランについてお教えいたします。
発達障害コースでは、様々な支援を提供し、お子様の成長と発達をサポートいたします。
料金は、ご家庭のニーズとお子様の状況に合わせて柔軟に選択いただけるプランがございます。
初回のカウンセリングやアセスメントに基づき、最適なサービスをご提案させていただきます。
料金につきましては、直接お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトをご参照ください。
お子様の将来に向けて、ふさわしい支援をご提供できることを心より願っております。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
不登校の子供たちの学習サポートの検討をしている保護者の皆様、すららのタブレット学習が不登校の子供たちに出席扱いになるのか、気になる点だと思います。
すららのタブレット学習は、不登校の子供たちにとって有益な教育ツールとなる可能性がありますが、出席扱いになるかどうかは学校や自治体によって異なります。
不登校の子供たちの出席状況に関しては、保護者と学校、地域の関係者との十分な協議が必要です。
具体的な扱いについては、関係機関に直接ご相談することをお勧めします。
不登校の子供たちにとって学習が継続できる環境づくりに向けて、適切なサポートが求められていますので、ぜひその点を考慮の上、問い合わせてみてください。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
ユーザーの皆様、私たちの記事へようこそ。
本日は、すららのキャンペーンコードの使い方について詳しく説明いたします。
すららでは、便利なキャンペーンコードをご利用いただき、さらなるお得なサービスを受けることが可能です。
では、使い方について順を追って説明いたします。
まず、ご利用のサービスや商品を選択し、お支払い画面に進んでください。
支払い画面に進む際に、キャンペーンコードを入力する欄がございます。
そちらに、お手元のキャンペーンコードを入力していただきます。
正確に入力していただくことで、割引や特典が適用されますので、お見逃しなく。
キャンペーンコードを利用する際には、有効期限を必ずご確認ください。
期限を過ぎたキャンペーンコードはご利用いただけませんので、ご注意ください。
また、一度のご利用でのみ有効な場合や特定商品にのみ適用される場合もございますので、ご利用前に利用条件をよくご確認ください。
最後になりますが、キャンペーンコードの使い方についてご理解いただけましたでしょうか。
この機会に、ぜひお得なサービスをご利用いただき、より充実したお買い物をお楽しみください。
何かご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
引き続きすららをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららをご利用いただきありがとうございます。
退会手続きについてお手伝いさせていただきます。
すららを退会する場合は、以下の手順に従っていただければと思います。
1. まず、お客様のアカウントにログインしてください。
2. ログイン後、画面右上のメニューアイコンをクリックしてください。
3. メニューから「アカウント設定」を選択してください。
4. アカウント設定ページで、「退会」または「アカウントを削除する」などの選択肢があるかと思いますので、それをクリックしてください。
5. 退会手続きが開始されますので、画面の指示に従って手続きを進めてください。
退会手続きが完了するまでの間、何かお困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
引き続きすららをご利用いただけますことを心より願っております。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららをご利用いただきありがとうございます。
入会金と毎月の受講料以外に追加料金が発生するかについてお答えいたします。
すららでは、基本プランに含まれる入会金と月額受講料以外に、特別なサービスやイベントへの参加等にかかる追加料金はございません。
レッスンやコンテンツの利用において予期せぬ費用が発生することはございませんので、安心してご利用いただけます。
料金体系に関する詳細や疑問点がございましたら、いつでもお問い合わせください。
ますますのご活躍をお祈り申し上げます。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
1人の受講料を支払った場合、兄弟や家族でそのサービスや製品を共有することは可能でしょうか?この点について明確なルールやポリシーが存在します。
一般的には、個々のサービスや製品によって異なりますが、ほとんどの場合、1人の受講料を支払った場合でも、他の家族メンバーと共有することは難しい場合があります。
利用規約や契約をよく確認することが重要です。
もし兄弟で共有したい場合は、事前に運営会社やサービス提供業者に問い合わせることがおすすめです。
彼らとの対話を通じて、最適な方法や手続きを尋ねることで、円滑な共有方法を見つけることができるかもしれません。
規約やポリシーを守りながら、問い合わせをすることで、トラブルを避けることができるでしょう。
どうぞ十分なご注意を払ってください。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには英語はありますか?このコースでは、英語の習得を目指すお子様のために様々な英語コンテンツが用意されています。
例えば、英語を学ぶためのオンラインゲームや問題集、さらには英語のリスニングやスピーキングの練習も行うことができます。
英語習得に興味のあるお子様にとって、すららの小学生コースは有益な学習環境となるでしょう。
英語に触れることで、お子様の語学力や国際交流能力の向上につながります。
是非、お子様の可能性を広げる英語学習の場としてすららの小学生コースをご検討ください。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチからは、様々なサポートを受けることができます。
コーチは個々の生徒のニーズや目標に合わせて指導を行い、学習の進捗をサポートします。
まず、コーチは生徒のレベルやニーズを詳しく把握し、カスタマイズされたレッスンプランを提供します。
その後、進捗や理解度を把握しながら、継続的なフィードバックやアドバイスを提供してくれます。
また、学習の詰まりや壁にぶつかった際には、モチベーションを高めるためのサポートも行ってくれます。
すららのコーチは、生徒がより効果的に学習を進められるよう、熱心にサポートしてくれます。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
今回は、「すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点」についてまとめました。
不登校の生徒が出席扱いになるためには、制度や申請手順を理解することが重要です。
出席扱いを受けるためには、保護者や学校との十分な連絡や手続きが必要となります。
また、出席扱いを受ける際には、注意点や期限についても正確に把握することが肝要です。
不登校の生徒が出席扱いになることで、学習意欲の向上や学校生活への復帰をサポートすることが期待されます。
制度や手順を適切に理解し、適切に申請手続きを行うことで、生徒の学習環境の改善や支援が可能となります。
不登校に悩む生徒や保護者にとって、出席扱い制度は重要な支援手段となることが予想されます。
最後に、不登校の生徒が出席扱いになることで、学校とのつながりを保ちながら学び続けることができる良好な環境が整うことを期待します。
制度や手順を適切に理解し、適切な申請を行うことで、生徒の学び舎や成長を支援する大きな一歩となるでしょう。
不登校の生徒や保護者にとって、出席扱い制度は希望と支援の架け橋となることを願っています。

